���{�o�c�J���������́A�l���]���E���^���x�Œ�����Ƃ̋Ɛь�����x������l���헪�R���T���^���g�ł��B
TEL. 048-824-0235
MAIL. info@corefocus.jp
- �g�b�v�y�[�W
- �@�g�D�}�l�W�����g�̖{�����l����i�R�����j
�g�D�}�l�W�����g�̖{�����l����i�R�����jCOLUMNS
�w���Ȃ���{��l�ƌ����ڂ��X���x�@�ivol.34�j
�u���T�͐l�����̃v���[���ɍs���Ă��܂��B�v�u�������A�����̓o�b�`�����낤�ȁH�v�u�R���ԓO�邵�Ċ����ȃv���[������������܂����B�v�u�Ȃʁ`�A���g�ȂW�Ȃ���B�v�u�͂��B�v�u�����ڂ��X���̖@����m��Ȃ��́H�v�u�u���`�A�����ł����B�v�u�����ڂłX�����܂����Ⴄ��B�v
�����ڂ��X���̖@���Ƃ́A�����郁���r�A���̖@���̂��Ƃ������Ă���B�A���o�[�g�E�����r�A���Ƃ����S���w�҂��wNONVERVAL COMMUNICATION�i���t���g��Ȃ��R�~���j�P�[�V�����j�x�Ƃ����_���Ŕ��\�����������ʂ��w���Ă���B�R�~���j�P�[�V�����̌n�̃r�W�l�X���ł͓S�ɂȂ��Ă���B
�����r�A���̖@���͑����̏ꍇ�A���̕����Ő��������B�R�~���j�P�[�V�����ő���ɓ`���̂́A�����ځi�����A�\��A�����A�������A�ԓx�j���T�T���A�b�����i���̃g�[���A�����A�傫���A�����j���R�W���A�b�̓��e�i���t�̈Ӗ��j���V���ɂȂ�B����ɉ����`��邩�́A�b�̓��e�ł͂Ȃ������ڂ�b�����Ō��܂�B
�������Ɍ����ڂ�b�����͑厖���낤���A�b�̓��e���قƂ�Ǔ`���Ȃ����Ă̂͌����߂�����Ȃ����B�����A�����߂��ł������B�����r�A���̎����́A�D��ہA���f�A����ۂ̂R��ނ̒P����g���A�R��ނ̕\��̎ʐ^�ƂR��ނ̘b�����̘^�����A���������g�ݍ��킹�Ŏ����A�ǂꂪ��������������������B
���̎����ł́A���t�͒P�ꃌ�x���ň����Ă���B�D��ۂ̒P��ihoney�Athanks�Adear�j�A���f�̒P��imaybe�Areally�Aoh�j�A����ۂ̒P��idon't�Abrute�Aterrible�j���g���B�h�b�̓��e���V���h�ƌ����Ă��邪�A�h�P��̈Ӗ����V���h�̂ق����������B�h�R�~���j�P�[�V�����h�ƈ�ʉ�����͖̂���������B
�������ʂ��������K�p�����̂́A�ЂƂ̒P������u�̏�ʂɌ�����B�ꔭ�|�ł��̖@����m���Ă��m�炸���g���Ă����B�|�����l�́h���Ȃ���{��l�h�B�u�����[�v�Ə��Č����Ă��S�R�|���Ȃ��B���́h�~�c�R�h�B�u�ǁ[�������܂���ł����v�ƕ|����Ō����Ă��S�R�Ӎ߂��`���Ȃ��B
�r�W�l�X�ɂ����Ă��A��u�̏�ʂł͂��̖@�������Ă͂܂�B���q�l�ւ̈��A��A�Г��ł̕Ԏ��Ȃǂ́A�P��̈Ӗ����������ڂ�b����������I�ƂȂ�B�P�ꂪ�Ȃ��蕶�͂ɂȂ������_�ŁA�T�T���A�R�W���A�V���̖@���͏�����B���͂�`����Ƃ��ɑ���ɓ`����ۂ́A���������l�����Ȃ��̂ł킩��Ȃ��B
�����r�A���̖@�����R�~���j�P�[�V�����S�ʂɂ��Ă͂߂Đ�������邱�Ƃ���������̂ŁA�ȏ�̂悤�ɂ����ł͂Ȃ��Ɣᔻ�������o�Ă��Ă���B�������A�ᔻ���Ă��������l���Ă݂����B���͂ŃR�~���j�P�[�V��������Ƃ��i�قƂ�ǂ̃R�~���j�P�[�V�����̏ꍇ�j�A���̎������ǂ����p�ł��邾�낤���B
�R�̗v�f�́AVisual�i���o�j�AVocal�i�����j�AVerval�i���t�j�́h�R��V�h�Ƃ�����B�����ł́A�R��V�����ꂼ�ꖵ�������Ƃ��A�ǂꂪ�`���₷�����������B�h���������Ƃ��h�Ƃ����̂����̎����̃|�C���g�Ƃ�����B�����̏�ʂł́A���ӎ��̂����ɂR��V�͖������Ă��܂��̂��낤�B
�b�̓��e�i���́j��`�������ʏ�̃R�~���j�P�[�V�����̏�ʂł́A���R�����b�̓��e��`���邱�Ƃ��ŏd�v�ł���A�R�~���j�P�[�V�����̖ړI�ɂȂ�B�������A���ӎ��̂����ɂR��V�������������ɂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�b�����e���������|�W�e�B�u�Ȃ̂ɁA�b�����͂�������ÂɂȂ��Ă���B
����̃R�~���j�P�[�V�����ł́A���t�̓��e�i�_���j���D�悳�ꂽ��A����i�\���b�����j���D�悳����ʂ����Ȃ��Ȃ��B�R��V�����Ă����ԂƂ�����B�b�̓��e�i�_���j�Ɗ���i�\���b�����j�ӎ�����ӎ��Ɉ����o���āA�R��V����������Ă��邩�ӎ����邱�Ƃ��˔j���ɂȂ邩������Ȃ��B
����͎v�����ƃ}�l�W�����g�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2015�N6��8���n
�w�T�O�̍ŐVver.������������x�@�ivol.33�j
�u�����o�c�v�������ɂ������āA�e�}�l�W���[�̂R�N��̃r�W�����������̂����B�v�u�r�W�����A�ł����H�v�u�F�̍l�����ł��邾��������悤�Ǝv���B�v�u�s�W�����Ȃ�m���Ă܂����ǁA�ŋߎq�����ł�������Ȃ̂ŁB�v�u�����A�r�W������m��Ȃ��̂��B�v�u�n�C�r�W��������Ȃ��ł���ˁB�B�v
�u�������ł���B�v�u�͂��A���݂܂���B�v�u����A�����݂̂�Ȃɕ����Ă݂悤�B�v�u�N�̂R�N��̃r�W�����́H�v�u���ܖZ������Ō�ł����ł����B�v�u������B�v�u�Ȃ�ŋ}�ɐԂ����n�̂��ƕ�����ł����H�v�u�����A�s�W�����B�v�u����Ȃ��Ƃ��A���̎d���̖Z���������Ƃ����Ă���������B�v
�}�l�W���[�ƕ����������킯�ł͂Ȃ��B�}�l�W���[�ƕ����ɂ̓r�W�����Ƃ����T�O���Ȃ������������B�T�O���Ȃ���A���̐l�̌����ɂ���͑��݂��Ȃ��B�r�W�����Ƃ����T�O���Ȃ���A�r�W�����ɂ��čl���悤���Ȃ��B�Ȃ����̂͂Ȃ��B�������A���̐l�ɂƂ��Ă���ƂȂ��̋��ڂ͗����I�Ȃ��̂��B
�A�����J�ɂ͌�����Ƃ����T�O���Ȃ����߁A�������������l�͂��Ȃ��炵���B�������Ⴆ�Γ��{�ŕ�炷�悤�ɂȂ��Č�����Ƃ����T�O��m��ƁA������ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����Ƃ����B���������邩�Ȃ����́A���̐l�̎��T�O�ŕς��B�T�O�̃f�[�^�x�[�X���ς��A�����鐢�E���ς��̂��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ŏ��̈�b���Љ�Ă��܂��B
���Â�����̌����`���ɁA�O�l�̐ΐ�E�l�Ɂu�������Ă���̂��v�Ɛq�˂��Ƃ�����b������B�ЂƂ�ڂ́A�u�����̗Ƃ��҂��ł���v�Ɠ������B�ӂ���ڂ́A�d���̎���x�߂��Ɂu���̍��ōō��̐ΐ�E�l�Ƃ��Ă̎d�������Ă���v�ƌ����B�O�l�ڂ́A����グ��ƁA��]�œ����P�����Ȃ���A�u�吹���������Ă���̂ł��v�Əq�ׂ��B���̎O�l�ڂ������^�̃}�l�W���[�ł���B��
�ЂƂ�ڂ̐E�l�ɂ́A�d���̋Z�p���ō��ɍ��߂�Ƃ����T�O�͂Ȃ����낤�B��l�ڂ̐E�l�ɂ́A�����̎d���͑吹�������邱�Ƃ��Ƃ����T�O�͂Ȃ����낤�B�������A�P�ɐ���Ƃ������̎d���ł͂Ȃ��āA�吹�������邱�Ƃ������̎d�����Ƃ����T�O��m������A�d���̐��E������Č����邩������Ȃ��B
�l�͊T�O�̃f�[�^�x�[�X�̍ŐV�o�[�W�����͈̔͂Ő��E�𑨂��Ă���B�Ƃ������A���͈̔͂̒��ł������E�𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������t�ɍl����A�T�O�̃f�[�^�x�[�X�����܂��X�V�i�o�[�W�����A�b�v�j�ł���A���܂Ō��Ă������E������Č�����B�������Ƃ̂Ȃ��������ڂ̑O�Ɍ����B
�X�V�͗e�Ղɂł�����̂��H�Ⴆ�X�}�z�̃A�v����V���ɃC���X�g�[������Ƃ��A�Â�OS�̂܂܂��Ɓh����OS�̃o�[�W�����ɂ͑Ή����Ă��܂���h�Ɣ��Ȑ鍐���������邱�Ƃ�����B�V�����T�O���f�[�^�x�[�X�ɒlj�����ꍇ���A�Â��T�O�œ����ł܂��Ă����Ԃł͂��̍X�V�͐������Ȃ����낤�B
�p�\�R���̏ꍇ�͗L�������킹�Ȃ��BWindowsXP�͍��ł́h�Ȃ����́h�Ƃ��������B�Â�OS���̂��g���Ȃ��B�d���Ȃ�����s�������тȂ���X�V����B�����ݑS�����Ȃ��̂ɁA�Ȃ��ʓ|�Ȃ��Ƃ�����K�v�����邩�B�l�͊�{�I�ɕێ�I���B�������A�X�V���Ă��܂��ΈӊO�Ƃ��̍�����Y��Ă��܂��B
���̐l�̊T�O�̃f�[�^�x�[�X���X�V����ɂ́A���̂悤�ɔ������I�ȊO�����K�v�ɂȂ邾�낤�B�ЂƂ�ЂƂ�̊T�O�̃f�[�^�x�[�X���X�V����A�g�D�ɐV�����T�O���Z������܂Ŏ��s����𑱂���B�g�D�}�l�W�����g�̖����́A�ŏ��Ƀ}�l�W���[�̃f�[�^�x�[�X���X�V���A�����g�D�S�̂Ɋg�U�����邱�Ƃ��B
�T�O�̃f�[�^�x�[�X�ɐV���ȊT�O���lj������ƁA�f�[�^�x�[�X���ŐV�o�[�W�����ɍX�V�����B�p�\�R����OS�Ɠ��l�ɁA��x�V�����o�[�W�����ɍX�V�����ΌÂ��o�[�W�����ɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ��B�ЂƂ�ЂƂ�̊T�O�̃f�[�^�x�[�X���ŐV�o�[�W�����ŋ��L���ꂽ�Ƃ��A�g�D�ɐV���������i���j�j��������B
����͗~���T�i�K���ƃ}�l�W�����g�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2015�N3��2���n
�w�v�l�̃G���g���s�[����̒E�o�x�@�ivol.32�j
�u�����W�܂��Ă���������R�͕������Ă��邾�낤�ȁB�v�u�����ŋߔ��オ�����Ă��邩��ł��ˁB�v�u�ǂ�������悢���F�̈ӌ������Ă���B�v�u�K��𑝂₷�����Ȃ��ł���B�v�u�łȂ��؍ݎ��Ԃ𑝂₷�����Ȃ��ł��B�v�u���̑O�ɂǂ��ɍs�����헪����邵���Ȃ��ł��傤�B�v
�u�����Ȃ����āA����ȂɎ��M������킯�B�v�u�����āA���ꂵ���Ȃ��ł���B�v�u���̓��������������̂��B�v�u���ꂵ���Ȃ�����A�����̗]�n���Ȃ��ł��傤�B�v�u�Ă������A�������ĂȂ���Ȃ��̂��B�v�u������ɂ��Ă��A���ꂵ������܂���B�v�u������ɂ��Ă����āA�}�W�b�N���[�h�g���ȁB�v
���̒������G�ɂȂ��Ă����ɂ�āA���ɑ��铚�������G�ɂȂ��Ă���B�ߋ��Ɠ����������J��Ԃ��Ă��A�ߋ��Ɠ������ʂ͏o���Ȃ��B�ߋ��̓����ɔ����Ȃ��A�V����������n��o���K�v������B�������A�����̑g�D�ł́h�����Ȃ��nj�Q�h�Ƃ������ׂ��A�v�l�̃G���g���s�[���ǂɂȂ邱�Ƃ������B
�����L�꒘�w�����Ɩ������̂������x�ł́A�ȉ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
���G���g���s�[�Ƃ͗��G���i�����_�����j��\���ړx�ł���B���ׂĂ̕����w�I�v���Z�X�́A�����̊g�U���ψ�ȃ����_����ԂɒB����悤�ɁA�G���g���s�[�ő�̕����֓����A�����ɒB���ďI���B������G���g���s�[����̖@���ƌĂԁB��
�G���g���s�[����̖@���ɂ��A����������̂͑S�Ė������Ɍ������Ă����A�ő�̖������̏�ԂŏI���B�V�������̂́A���R�ƌÂ��Ȃ��Ă����B�Y��Ȃ��̂́A���R�Ɖ����Ȃ��Ă����B�����āA���̖@���ɋt�����͂Ȃ��B�Â����̂����R�ƐV�����Ȃ�����A�������̂����R���Y��ɂȂ�����͂��Ȃ��B
�����Ă�����͓̂����ł���A���ł���A���̎�����S������Ȃ�Ύ����Ɍ������Đ����Ă����B�ŏI�I�ɖ����̍זE�����Ă��������́A���S�Ȗ������̏�ԁi���j�Ɏ���B�ꌩ����ƁA�����Ɍ������đS�̂����X�ɐ����Ă����悤�Ɍ�����B���������ۂ́A�����ƃ_�C�i�~�b�N�ȓ������N�����Ă���B
�w�����Ɩ������̂������x�ł́A����ɂ����������Ă��܂��B
�������Ă��鐶���́A�₦���G���g���s�[�債����B�܂�A���̏�Ԃ��Ӗ�����G���g���s�[�ő�Ƃ����댯�ȏ�Ԃɋ߂Â��Ă����X��������B���������̂悤�ȏ�ԂɊׂ�Ȃ��悤�ɂ���A���Ȃ킿���������Ă������߂̗B��̕��@�́A���͂̊����畉�̃G���g���s�[��������������邱�Ƃł���B���ہA�����͏�ɕ��̃G���g���s�[���h�H�ׂ�h���Ƃɂ���Đ����Ă���B��
�l�͐H�ׂȂ���Ύ���ł��܂��B���̂��߂ɐH�ׂ邩�Ɩ����A������G�l���M�[��⋋���邽�߂ƕ��ʂ͓�����B����ŃG�l���M�[������Ή��ł��悳���������A�������i�����Ă��Ȃ��j���̂����H�ׂ��Ȃ��B�����Ă��鐶���͓��X�������Ɍ����A�O����i�������j������������Ȃ��Ɛ������Ȃ��B
�l�̐g�̂��v�l�����R�Ȃ�A�v�l�������悤�ɍl�����邾�낤�B�l���𐔏\�N������A�����̒m����o�����~�ς���Ă���B�����Ă�����x�K�v�Ȓm����o��������ꂽ�Ǝv���ƁA�h�����w�Ԃ��̂͂Ȃ��h�I�ȁh�������傠����h�̔��z�ɂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A�v�l�̃G���g���s�[�����X���債�Ă���B
���܂Őςݏグ���ĂЂƂ̒����ɂȂ����v�l�́A���R�̖@���Ƃ��ē��X�������ւƌ������Ă���B�Ⴆ�A���t�̈Ӗ��͓��X�Â��Ȃ�A���t��g�ݍ��킹���T�O�����X�Â��Ȃ�B�ŏI�I�ɂ́A���݂̊��ł͎g�����̂ɂȂ�Ȃ����t��T�O�i���j�Ɏ���B���Ɏ���Ώ_��̓[���i�h�����Ȃ��h�j�ɂȂ�B
�w�����Ɩ������̂������x�ł́A�܂������������Ă��܂��B
���G���g���s�[����̖@���́A�e�͂Ȃ����Ԃ��\�����鐬���ɂ��~�肩����B�����q�͎_�����ꕪ�f�����B�W���̂͗��U���A�����͗����B�^���p�N���͑����������ϐ�����B�������A�����₪�Ă͕���\�������������Đ��肵�ĕ������A���̂悤�ȗ��G�����~�ς�����������A��ɍč\�z���s�����Ƃ��ł���A���ʓI�ɂ��̂����݂́A���傷��G���g���s�[���n�̊O���Ɏ̂Ă邱�ƂɂȂ�B��
�₪�Ă͖��ɗ����Ȃ��Ȃ錾�t��T�O�������Đ��肵�ĕ������A�v�l���ł܂��Ă��܂��i���Ɏ���j���������A��ɐV���Ȍ��t��T�O���č\�����Ă����B���̍�Ƃ��Ӑ}�I�ɍs�����Ƃ��ƂŁA�v�l�̃G���g���s�[����E�o�ł���B�Ⴆ�A�������������Ȃ�����̌��t��T�O�ɐϋɓI�ɐG���悤�ɂ���B
�w�����Ɩ������̂������x�ł́A�����Ă����������Ă��܂��B
���G���g���s�[����̖@���ɍR���B��̕��@�́A�V�X�e���̑ϋv���ƍ\�����������邱�Ƃł͂Ȃ��A�ނ��낻�̂����ݎ��̂𗬂�̒��ɒu�����ƂȂ̂ł���B�܂藬�ꂱ�����A�����̓����ɕK�R�I�ɔ�������G���g���s�[��r�o����@�\��S���Ă��邱�ƂɂȂ�̂��B��
�v�l�Ƃ͌��t��T�O�̐ςݏd�˂ł͂Ȃ��A���t��T�O�̗��ꂾ�Ƒ�����B������A�����낭�̂悤�ȁh������h�͂Ȃ��B����Ă��邩�A����Ă��Ȃ����B�����̎v�l��������������łȂ��A�ނ��날���ĕ����Ďv�l�𗬂�̒��ɒu���B�g�D�}�l�W�����g�́A�g�D�Ɏv�l�̗��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����͊T�O�Ƒ��݂̊W�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2015�N2��16���n
�w�F���̃p���h�b�N�X�ƃo�J�̕ǁx�@�ivol.31�j
�u�Ǘ��E�̂��߂̃R�~���j�P�[�V�����u�����B�v�u��������������́B�v�u�ق�ƁA�Z�����Ă���ȉɂ͂Ȃ���B�v�u�R�~���j�P�[�V���������肾����o��������ł���B�v�u���̒ʂ�B�v�u�t�ɃR�~���j�P�[�V�����Ƃ͉����������Ă��܂��傤�B�v�u�������ȁA�̂����ȍu�t�Ɋ������Ă��邩�B�v
�u�R�~���j�P�[�V�����ő厖�Ȃ��Ƃ͂R�ł��B�v�u�����Ȃ�̂�����ȁB�i�S�̐��j�v�u�ЂƂڂ́A����̘b���悭�������Ƃł��B�v�u�ӂށB�v�u�悢�Ǘ��E�Ƃ́A�����̘b���悭�����l�ł��B�v�u�搶�A���ꂪ�܂��Ɏ��̖�������Ă邱�Ƃł��B�l�̘b�����Ă����̂́A�������~���H�������E�E�E�B�v
�u����A�����̕������̘b���炵�������ł��ˁB�v�u��������B�v�u���̈̂����ȍu�t�����ɂȂ����ł��傤�ˁB�v�u������O�̘b���邾���ōu�t���Ă�����������B�v�u�܂������������肵�܂�����B�v�u���牴������ɍu�t����Ă���B�v�u�����ł��ˁB�v�u�܂��Z�����Ė��������ǂȁA�͂͂́B�v
�����͑���̘b���Ă���ƌ����l�قǁA�{���͑���̘b���Ă��Ȃ��B�����͑���̘b���Ă��Ȃ��ƌ����l�قǁA�{���͑���̘b���Ă���B�܂��𒍈Ӑ[���ώ@���Ă݂�ƁA������������������Ȃ��Ă���B���̔F���̃p���h�b�N�X�i�t���j�Ƃ����ׂ����ۂ́A�ǂ����琶�܂��̂��낤���B
������O�̂��Ƃ����A�l�͎����̑S�̑��Ō��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��ȊO�̊e�����͉��Ƃ����ߋ����Ō��邱�Ƃ��ł��邪�A�����̊�̑S�̑��͐�ɐ��ł͌����Ȃ��B�����̊�́A�B�ꎩ�����������Ō��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B������K�R�Ƃ��āA�����̑S�̑����q�ϓI�ɐ��Ō��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
���ł͂Ȃ��������̑S�̑���������@������B�r�f�I���B�Ⴆ�A�X�L�[�������Ă���p���r�f�I�ɎB���Č��Ă݂�B�����ɏՌ��̎��������邱�ƂɂȂ�B�����̃C���[�W�ƌ����̊Ԃɂ́A�Q�����N���̍�������炵���B���Ԃ��Ԏ�����F�߂ĉ��P���悤�ɂ��A�����̎p�Ō��Ȃ���C�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�l�͎������v���܂܂ɁA�����̐g�̂������Ƃ��ł��Ȃ��B�g�b�v�A�X���[�g�ł������X�̌������g���[�j���O��ӂ�A�����̎v���ʂ�ɐg�̂������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B�����̎v���Ɛg�̂̓����Ƃ́A�Ȃ������݂��ɉ������݂ɂȂ��Ă���B�v���Ɛg�̂̊W�́A�ӎ��Ɩ��ӎ��̊W�Ɠ��ӂ��낤�B
�i�ӎ��I�ȁj�v���Ɓi���ӎ��I�ȁj�s���͈�v���Ă���悤�Ɍ����邪�A���݂��ɓƗ����Ă���Ƒ����Ă݂�B�������v�����ʂ�ɁA�����̐g�̂������Ă��Ȃ��������ꂢ�ƍl����B�����̎v���͈ӎ��I�ɓ��̒�����r�����āA�����̐g�̂͂ǂ������Ă��邾�낤���Ǝ��o�I�Ɂi�q�ϓI�Ɂj�`�F�b�N���Ă݂�B
�ǂ�������l�͖��ӎ��̍s���Ɏ��o�I�ɂȂ��̂��B���̖₢�͔F���̃p���h�b�N�X�ɂȂ���B�u�l�̘b���Ă��Ȃ��v�Ƃ������t�́A�b�����ƂɎ��o�I�����炱�������錾�t���낤�B����Łu�l�̘b���Ă���v�Ƃ������t�́A�b�����Ƃɖ����o�����炱���f��I�Ɍ�����̂��낤�B
�b�����Ƃɖ����o�ȁu�l�̘b���Ă���v��i���A��������u�l�̘b���Ă��������v�ƌ�����B�u���������Ă��邾�낤�i���O�̓o�J���j�v�Əu���ɕԂ��B�����ɗ{�V�Ўi���̂����h�o�J�̕ǁh�������ɂȂ�B���҂̊ԂɃo�J�̕ǂ������͂�����Ԃ́A���݂��ɗ������������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�h�o�J�̕ǁh�����߂ɂ́A�F���̃o���h�b�N�X�����o����B�u�`�ł��Ă���v�ƌ����Ă���ƋC�Â�����A�낤���Ǝv���悤�ɂ���B�����āu�`�ł��Ă��Ȃ���������Ȃ��v�ƌ��������Ă݂�B�������邱�ƂŁA�����o�Ȃ܂܂ł͌����ɂ��������̐g�̂̓�����F���ł���悤�ɂȂ��Ă���B
�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃ́h�o�J�̕ǁh���Ă������Ƃ��A�g�D�}�l�W�����g�̖����̂ЂƂ��낤�B�ǂ��܂ł����Ȃ��܂ł��A���̍�����Ⴍ���Ă����B�ǂ̍������Ⴍ�Ȃ�ɂ�āA������Ă����ӌ���A�C�f�A���s�������悤�ɂȂ�B����炪�Ԃ��荇���A���܂Ō������Ƃ̂Ȃ��g�D�̗͂����̎p�������B
����͎v�l�̃t���[�ƃX�g�b�N�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2015�N2��2���n
�w���G�n�̑g�D�}�l�W�����g�i��j�x�@�ivol.30�j
�u�ڋq�ɋώ��̃T�[�r�X����邽�߂ɁA�ڋq�}�j���A�������܂��傤�B�v�u�Ј��������Ă������A�l�ɂ���ăT�[�r�X�̎����Ⴄ�͍̂���ȁB�v�u���Ƃ��A���H�p�̃i�b�c�͑܂���o���Ē���Ƃ��B�v�u����͏d�v�Ȃ��Ƃ��B�v�u�ڋq�}�j���A���őg�D��ϊv���āA����{����ڎw���܂��傤�B�v�u�ӂށB�v
�u�ڋq�}�j���A���̌��ʂ͂ǂ����H�v�u�}�j���A������点��̂͑�ςł������A�Ȃ�Ƃ��g�D�ɐZ�����܂����B�v�u�\��ʂ蔄����{�������̂��B�v�u���ꂪ�B�B�v�u�ǂ��������Ƃ��H�v�u�Ј����}�j���A���̂��Ƃ���l���āA���q�l�̂��Ƃ��l���Ȃ��Ȃ�܂����B�v�u�����`�A�}�j���A���͂����ɔp�~����B�v
�u����{����ڎw���ē��������ڋq�}�j���A���ł����A��������p�~���邱�ƂɂȂ�܂����B�v�u����������J���Ċo�����̂ɁB�v�u���݂܂���B�v�u��������ǂ��������ł����H�v�u�}�j���A���͂���܂���A�F���R�ɐڋq���Ă��������B�v�u�͂��B�v�u�e�����x�X�g�̕��@���l���Ď��s����̂ł��B�v
�u�}�j���A���p�~�̌��ʂ͂ǂ����H�v�u��i�͎w�������Ȃ��悤�ɂ��āA�e�������R�ɐڋq����悤�ɂ��܂����B�v�u����ŁB�v�u���オ������Ј��Ƃ�����Ȃ��Ј��̍����L����܂����B�v�u���オ������Ј������߂���A�E�g����Ȃ����B�v�u�����Ȃ�ł��B�v�u�Ȃ�Ƃ�����A�����`�B�v�u�ӂ��B�v
���G�n�̓����Ƃ��āA�h�J�I�X�̉��h�Ƃ����T�O������B�J�I�X�ichaos�j�Ƃ͒P�������Ă����A�������ō��ׂƂ�����Ԃ̂��Ƃ��B���G�n�͒����ƃJ�I�X�̋��E�ɂ���h�J�I�X�̉��h�ŁA�o�����X�̂悢�_��ȑg�D���ێ����邱�Ƃ��ł���B�g�D�͒����Ǝ��R�́h�J�I�X�̉��h�ŁA���́h�����Ă���h�p�������B
�}�j���A�������`�ł����ƒ����ɕ肷����B���C��`�ł����ƃJ�I�X�ɕ肷����B���̋��E�ɂ���h�J�I�X�̉��h�őg�D���@�\������B�g�D�}�l�W�����g�́h�J�I�X�̉��h��ڎw���B�������c�_����Ƃ��A�������͓_�Ɋׂ邱�Ƃ������B�}�j���A���͂悢���������H�������A�œK�ȓ����͂��̊Ԃɑ��݂���B
�}�j���A����_����ꍇ�́A�}�j���A���̒�`�����ɂȂ��Ă��邾�낤�B�u���Ђ̃}�j���A���Ƃ͉����H�v����c�_���n�߂�B�@�B�������}�j���A�����C���[�W�Ƃ��ċ������߂ɁA�ڍׂȍ�Ƃ̎菇�����}�j���A�����ƍl���������B�������A�l������̐ڋq�Ɩ��ł���A�h�J�I�X�̉��h�ɍs�������Ƃ�ړI�Ƃ���B
�w���G�n����x�ł́A�ȉ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
���J�I�X�̉��ł͈���ԈႦ�J�I�X�̊C���Ɉ��ݍ��܂�A�܂����ł͓����̒n���҂��\���Ă���B�����̖{���Ƃ����̂͂��̂��傤�Nj��E�̕����ŁA�K���Ƀo�����X���Ƃ낤�Ƃ��Ă���̂�������Ȃ��B���̍I���Ȏd�g�݂����R�ɔ���������Ƃ����_���d�v�Ȃ̂ł���B��
���G�n�ł���g�D�́A�J�I�X�̉��ŕK���Ƀo�����X����낤�Ƃ��Ă���Ƃ��Ɂh�����Ă���h��ԂɂȂ�B�g�D�}�l�W�����g�́A�g�D�������̂ق��ɐU�ꂷ���ĂȂ����A�J�I�X�̂ق��ɐU�ꂷ���ĂȂ�������Ɋώ@����B��x�ǂ��炩�Ɍ������ƁA�����̗͂�����邾�낤�B������߂��A�o�����X�����ɂ����B
���G�n�̃J�I�X�ł́A����Ɂh�����l�̉s�q���h�Ƃ�������������B�u�u���W���Œ����H�����Ƃ��ꂪ��������ăA�����J�ŗ����N����v�Ƃ�����g����A�h�o�^�t���C���ʁh�ƌĂ��B�킸���ȏ����l�̍��قɑ��āA���ʂ��傫���قȂ�Ƃ����������B�����̂킸���ȁh��炬�h���A���ʂɑ傫�ȉe�����y�ڂ��B
�t�Ɍ����A���G�n�ɂ킸���ȁh��炬�h��^���邱�Ƃɂ���āA���ʂ�傫���ς��邱�Ƃ��ł���B�����g�D�ɂ��Ă͂߂�A�ЂƂ�܂��͏����̃����o�[���g�D�Ɂh��炬�h��^���邱�ƂŁA�g�D��傫���ς��邱�Ƃ��ł���B���̂Ƃ��A�h��炬�h���g�D�̕��G�n�Ɂh�Ђ�������h���ǂ��������ɂȂ��Ă���B
�g�D�}�l�W�����g�́A����ׂ��ϊv�̕����Ɍ������Ă킸���ȁh��炬�h���N�����B�������A���̂�炬���g�D�̕��G�n�ɉ^�悭�Ђ��������Ă��A���̌�̓����͗\���ł��Ȃ��B��炬���N�������Ƃ��@�m������A���̌�ǂ��ω����Ă������ώ@����B�ω��ɖ�肪���ꂽ��A���₭���́h��炬�h���N�����B
�g�D�G�n�Ƃ����h�����Ă���V�X�e���h�Ƒ�����ƁA�g�D�}�l�W�����g�̗����ʒu�������Ă���B�����Ă��铮����A���ɗႦ��Ȃ�A�@�B�̂悤�ɃR���g���[���͂ł��Ȃ��B���炩�̐��b��������A���̔�����҂����Ȃ��B�g�D���R���g���[�����悤�Ƃ����A�g�D����ĂĂ����̂��g�D�}�l�W�����g��������Ȃ��B
����͔F���̃p���h�b�N�X�ƃo�J�̕ǂɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2015�N1��19���n
�w�@�cSA�͑��݂��邩�i�ԊO�ҁj�x�@�ivol.29�j
��N���ɍ��V�[�Y���̏�����ɍs���ė����B�u����A�Җ]�̃X�L�[�V�[�Y��������Ă����ˁB�v�u�n���^�}���ƃn���^�[�}�E���e�����A�v���Ԃ肾�ȁB�v�u���k���͋Ă��ĉ��K����B�v�u�Ƃ���Œ��H�͂ǂ�����H�v�u���k���̊��IC������邩��A�ŏ��̘@�cSA�Ɋ��̂͂ǂ��H�v�u�����ˁA�������悤�B�v
�u�����͑S���I�ɐ���̗\��Ȃ�ˁB�v�u��D�̃X�L�[���a�ɂȂ肻���B�v�u�Ⴊ��������X�L�[�ꂪ����̂ɁA�����Ԃ̋M�d�Ȑ���Ɋ���̂��ґ�Ȃ̂�ˁB�v�u�����ĂĂ悩�����Ǝv���B�v�u����A����PA�͉H�������āB�v�u�@�cSA�Ȃ������ˁB�v�u���IC����O�����������B�v�u�Ƃ��ă{�P�����B�B�v
���̂Ƃ������ɂ������ɂ��@�cSA�͑��݂��Ȃ������B��l���ĕW�������������̂��낤���B���ꂾ���傫���Č��₷���W�����A��l�̖ڂɓ����Ă��Ȃ��͂����Ȃ��B���E�ɂ͓����Ă������A�F������Ȃ������Ƃ�����Ԃ��낤�B�������A���̂Ƃ���l�ɂƂ��Ę@�cSA�͂��������Ƃ����A��͂�Ȃ������̂��B
����͎�ςł����āA�q�ϓI�ɂ���͎̂����ł��傤�B���ʂ͂����Ԃ����̂��I�`���B�ЂƂ�ЂƂ�̎�ςƂ͕ʂɁA�q�ϓI�ɗB��̐��E�����݂��Ă���B����������Ƃ����ł���C�����邪�A�{���ɂ����Ȃ̂��낤���B�����ɂƂ��ẮA���̂Ƃ��@�cSA���Ȃ������͎̂����Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�l���L����H��Ƃ��A�h���o�ɓ��������F������Ȃ������h�����͎v���o����Ȃ����낤�B�Ȃ���̐l�ɂƂ��Ă̎����́A���̐l���F���������ۂɌ�����B���̐l���F�����Ă��������̏W���̂��A���̐l�ɂƂ��Ă̐��E���B�q�ϓI�ȗB��̐��E�����Ă���̂ł͂Ȃ��A�ЂƂ�ЂƂ肪�Ǝ��̐��E�����Ă���B
�����Ȃ�Ƌq�ϓI�ȗB��̐��E�����݂��邩�ǂ��������łȂ��A�ЂƂ�ЂƂ肪�F�����Ă��鐢�E���Ⴄ���Ƃ����ɂȂ�B�������F�����Ă��������������ɂƂ��Ă̐��E�̑S�Ăł���A����͑��l�ɂƂ��Ă̐��E�Ƃ͑S���Ⴄ�Ƃ����O��n�߂�B�Ⴄ���E�̐l�Ƃǂ����ǂ�����Ă������B
�q�ϓI�ȗB��̐��E������Ƃ��āA���̑S�Ă��ЂƂ�̐l�Ԃ��F�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�l���ꂼ�ꂪ�A�����Ȃ�ɐ��E��ҏW������Ȃ��B�l���ꂼ�ꂪ�A���E�̕ҏW�҂��B���̐l�͂ǂ�ȁi���ӎ��́j�ҏW���j�Ő��E��ҏW���Ă���̂��낤���A�Ƃ������_�ő��҂����邱�Ƃ��ł���B
�ЂƂ�ЂƂ肪���E��ҏW���Ă���Ƃ�����A�ƑP�I�ɂȂ�����A�ے�I�ɂȂ�����A���삪�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ����邾�낤�B�ҏW�̎�����L������ɂ͂ǂ�������悢���A�������g�ɂ����҂ɂ��₢�����Ă����B���݂��������Ƃ悢���E�����邽�߂̕��@���A�R�~���j�P�[�V�����Ȃ̂�������Ȃ��B
�t�Ɍ����A���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������Ȃ���ΐ��E���L�����Ȃ��B�Ⴄ���E�̐l�тƂ��Ԃ��荇���āA���ꂼ��ɐV�������E���L���Ă����B���E���L����A���܂Ō����Ȃ��������E��������悤�ɂȂ�B�l����������Ƃ́A����̐��E���L���Ă������ƂȂ̂�������Ȃ��B
��N���̎����̐��E�ɘ@�cSA�͑��݂��Ȃ������B�������A����ɓ���������SA�ŋɏ�̏Ă����ăs���V�L�ɏo����Ƃ��ł����B�@�cSA�Ɋ���Ă�����A���̂Ƃ��̐��E�ɍ���SA�͑��݂��Ȃ������B�D�ꂽ���E�̕ҏW�҂Ƃ́A�\�蒲�a������������Ƃ��ł���l�Ȃ̂�������Ȃ��B
����͕��G�n�̑g�D�}�l�W�����g�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2015�N1��3���n
�w���G�n�̑g�D�}�l�W�����g�i�O�j�x�@�ivol.28�j
�u�g�D�������Ă�����Č����Ă��A�Ȃs���Ƃ��Ȃ��ȁB�v�u�����ł��ˁA�g�D���̂��͖̂ڂɌ����Ȃ��ł�����ˁB�v�u�����Ȃ�A�g�D�������Ă�����Č���ꂽ��ǂ���������̂�B�v�u�������ɁA�g�D�Ƃ����͎̂��̂��Ȃ��ł���ˁB�v�u����A�ڂɌ����Ȃ��T�O�����瑨���Â炢�ȁB�v
�u�g�D���Ă������̂�����Ǝv���ƁA�g�D�}���g�D���Ǝv���Ă��܂��ˁB�v�u�����A�g�D�}�����܂�����Ƒg�D�����܂������C�����Ă��܂��B�v�u�g�D�}���v�}�ƂȂ�A�v�}�ɏ]���đg�D�����肠����B�v�u�ڂɌ������̂͂������ǁA�ڂő�������ƍ��x�͕��̂悤�Ɉ��������ɂȂ�B�v
�u���`��A�g�D�}�͂ǂ����Ă��h�����ĂȂ��h�Ȃ��B�v�u�ł��悭�l����ƁA�g�D�͐����Ă���l�Ԃł����Ă��܂��ˁB�v�u�����A������O���B�v�u�����Ă���l�Ԃ������W�܂��āA�g�D�ɂȂ�����@�B�ɕς����Ă��Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�v�u��������A�S�Y����J���ċ�͓S���X�X�X�ɏ��K�v���Ȃ����̂ȁB�v
�u���������ς�g�D�́h�����Ă���h��ł��B�v�u�ӂށB�v�u�����Ă���V�X�e���͕��G�n������A���G�n�̓�����m��Αg�D�̐����l��������B�v�u���G�n�̓�����m���āA�g�D���Ă���V�X�e���Ƒ�����̂��ȁB�v�u�l�Ԃ́A�h��������h���Ƃ����h����������h�̂ł��B�v�u�l�͌��������̂������Ȃ��A���B�v
���G�n�̊�{�I�ȓ����Ƃ��āA�h�n���h�Ƃ������ۂ�����B�h�n�h�͑n������A�h���h�͔�����B�܂�A���܂łȂ��������̂��n������A�V���ɏo������Ƃ����Ӗ����B�l�͂��ꂼ��ŗL�̐��i�������Ă��邪�A�l���W�܂��đg�D�ɂȂ����Ƃ��A���R�Ƃ��̑g�D�̕��������܂��B��Ђł����A�Е��Ƃ������̂��ł�������B
�w���G�n����x�ł́A�ȉ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
���n���Ƃ́A�����̗v�f�����ꂼ��Ǐ��I�ȑ��ݍ�p�����邱�Ƃɂ���āA�S�̓I�Ȑ��������܂�A���̑S�̓I�Ȑ������X�̗v�f�̐����ɉe����^����悤�Ȃ����݂̂��Ƃł���B��
���G�n�ł���g�D�ł́A��ɂ��́h�n���h���ۂ��N�����Ă���B�g�D�S�̂̐����́A���R�ɑn����B�����āA���̑n��ꂽ�g�D�̐����ɉe������āA�e�l�̐������ω�����B�g�D�̒��ł́A���̖ڂɌ����Ȃ����ݍ�p���J��Ԃ����B������A���[�������邱�ƂŁA���[���ʂ�̑g�D�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���[��������͖̂��ʂȓw�͂Ȃ̂��B�����A�g�D�Ƀ��[�����Ȃ�������ǂ��Ȃ邾�낤���B���[�����Ȃ��Ă��n���͋N����B�g�D�S�̂̐����i�����j�͎��R�Ƃł��Ă��܂��B�����āA���̑g�D�����Ɍl�͉e������B�Ƃ������Ƃ́A�S���\���ł��Ȃ������őg�D�������`�Â����A�l�͂��̕����ɉe�������B
�h�n���h�́A�h���ȑg�D���h�Ƃ������B�g�D�͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA����I�Ɏ���̕������`�Â����Ă����B�S�Ď��R�ɔC����A�ǂ�ȕ������ł������邩�S���킩��Ȃ��B�ŏ��ɑg�D������Â��郋�[���̂悤�Ȃ��̂��Ȃ���A�g�D�����͖\������B���R�Ɏ��ȑg�D�����āA�R���g���[�����邱�Ƃ�����ɂȂ�B
���G�n�̑g�D���h�n���h���Ă��܂��ȏ�A���[���ɂ���ĊǗ����邱�Ƃ͍���B�������A�g�D������Â�����̂Ƃ��Ắh���[���h�͕K�v�ɂȂ�B�g�D�Ƀ��[����x���������Ƃ��A�O�҂̎��_�ƌ�҂̎��_�ł͂P�W�O�x���̖������ς���Ă��܂��B���G�n�̑g�D�ɂƂ��āA��҂́h���[���h���}�l�W�����g�̌��ɂȂ�B
����͈����������G�n�̑g�D�}�l�W�����g�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N12��13���n
�@�@�@�@�@
�w���[���ƃV�X�e���_�C�i�~�N�X�x�@�ivol.27�j
�u�������N�̋Ɛђ����Ŕj���邽�߂ɁA�}�b�L���[�[�̂VS�őg�D���v��f�s���܂��B�v�u���`�A���ɎВ����{�C�o�������B�v�uShared Value�́A�h���Ă��܂��������I�h�ł��B�v�u�ف`�B�v�u��������o�c�헪�A�g�D�}�A�l�����x�ɗ��Ƃ����݂܂����B�v�u�ӂށB�v�u����ȍ�Ƃł������A���Ƀn�[�h�̂RS���������܂����B�v
�u���͊F����̔Ԃł��B�v�u�����B�v�u�n�[�h�̂RS���g���āA�\�t�g�̂RS�����������Ă��������B�v�u���̂�������B�v�u�o�c�헪�A�g�D�}�A�l�����x�ɏ]���āA�g�D�����A�l�ށA�X�L��������グ��̂ł��B�v�u�Ȃ�قǁA�����̃��[���ɏ]���ē����悢�̂��ȁB�v�u���̒ʂ�ł��B�v�u��`���A�撣��}�b�X���I�I�v
�l���W�܂��������ł͑g�D�ɂȂ�Ȃ��B�ЂƂ̖ړI�Ɍ������Đ��ʂ��ő�ɐ��ݏo���悤�ɁA�Ӑ}�I�ɓ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A�g�D�}�l�W�����g�����Ȃ���A�l�̏W�܂肪�g�D�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B���̂Ƃ��ɁA�g�D�Ƃ������̂��ǂ������邩�ɂ���āA�A�v���[�`�̂�����������Ă���B
��L�́A���[��������đg�D�����Ƃ����A�v���[�`���@���B���̍l���̉��ɂ́A���[���ɂ���đg�D���R���g���[�����悤�i�ł���j�Ƃ����v�z������B�ǂ��炩�Ƃ����ƌl�l�Ƀt�H�[�J�X��������A��Ƃł���ΎЈ��Ƃ����ЂƂ̒��ۊT�O�Ƀt�H�[�J�X���Ă���B�@����K�������̍l�����Ɠ��l���B
�g�D�̗��z�I�Ȍ`��`���āA����Ɍl�����킹�Ă����Η��z�̑g�D�ɋ߂Â��Ă����B�_���I�ɍl����ƁA���̂��Ƃ͐��������Ɏv����B���t�͘_���i���S�X�j������A���ł͂�����������B�������A���̒��Ř_���I�ɃV���~���[�V�����ł������Ƃ��A�����ɂ͂��̒ʂ�ɂȂ�Ȃ����Ƃ������B
���t�͘_���łł��Ă��邪�A�����͘_�������łł��Ă��Ȃ��B�h���t�ɂł��Ȃ��h�Ƃ������Ƃ�����B���̂Ƃ������͘_�����Ă���B���B�g�Q���V���^�C���͌������B�u��肦�ʂ��̂ɂ��ẮA���ق��˂Ȃ�Ȃ��B�v���������āA�g�D���_���̑��ɂǂ̂悤�Ȑ��������̂��A����ɍl����K�v������B
���[���őg�D�����Ƃ������Ƃ́A�l�̓��[���ʂ�ɓ������̂Ƃ����O��Ɋ�Â��Ă���B�g�D�������Ԃ̂悤�ȋ@�B�I�ȃV�X�e���ɗႦ�āA�S�Ẵp�[�c���v�ʂ�ɓ����ō����\������ƍl����B�������h�@�B�I�h�ɑ�����Ƃ킩��₷�����A�킩��₷�����ƂƐ^���ł��邱�Ƃ͕ʂ̂��Ƃ��B
�@�B�I�ɑ�����Ƃ́A�Ȋw�I�ɑ�����ƌ��������邱�Ƃ��ł���B�Ȋw�I�ɃV�X�e���𑨂���Ƃ́A�V�X�e�������̍\������v�f�ɕ������ė������Ă������Ƃ��B��������A���̃V�X�e���̑S�e���𖾂����B�ЂƂ̐��������h�ÓI�ȁh�V�X�e�����ڂ̑O�Ɍ����B�l�͊e���̃x�X�g�Ȗ����Ŋւ�荇���Ă���B
�g�D���������邱�Ƃ�����Ƃ���A����ł悢�B�������A���s�͖��킾�B���ɂ����̎��ォ��A���������Ƃ݂����g�D���i���ɑ������Ƃ͂Ȃ��B�g�D�́A�_�������Ƃ���ŏ�ɕω��������Ă���B�ɉh���鎞��������A���ނ��鎞��������B���N�ȂƂ�������A�a�C�̂Ƃ�������B�g�D���g�����Ă���h�̂��B
�h�����Ă���h�V�X�e���Ȃ�A�v�f�ɕ������Ă��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�l�Ԃ̐g�̂�S�Ẵp�[�c�ɕ������Ă��A�����Ă���l�Ԃ𗝉����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̉Ȋw�I�ȕ��@�̌��E���鎎�݂Ƃ��āA�����Ă���V�X�e�����h���G�n�h�Ƃ����V�X�e���icomplex
system�j�Ƃ��đ����悤�Ƃ�����@������B
��됒�A�����`�v���w���G�n����x�ł́A���G�n�ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
���o���o���ɕ����ł���v�f�̒P���ȑg�ݍ��킹�őS�̂��\������Ă���V�X�e���ł͂Ȃ��A�o���o���ɂ��Ă݂�Ɩ{�������������Ă��܂��悤�ȓ���ȃV�X�e�����w���G�x�icomplex�j�ȃV�X�e���ƌĂԁB��
�o���o���ɂ��Ă݂�ƃV�X�e���̖{�������������Ă��܂��B�������Ɂh�����Ă���h���̂́A�������G�Ȃ��̂��W�����ĂЂƂ̑S�̂ƂȂ�A�S�̂Ƃ��ĂЂƂ̐����i���A�C�f���e�B�e�B�j�����悤�Ɏv����B�悭���i���͂Ȃǂł́A�����̗v�f�ɕ������Đ�������邪�A�������܂��ꂽ�C������̂͂��̂��߂��B
�w���G�n����x�ł́A����Ɉȉ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
�����̃V�X�e�����\�����Ă���v�f�͊e���̃��[���ɏ]���ċ@�\���Ă���A�Ǐ��I�ȑ��ݍ�p�ɂ���đS�̂̏�ԁE�U���������肳���B�����Ă����̑S�̓I�ȐU���������ƂɌX�̍\���v�f�̃��[���E�@�\�E�W�����ω����Ă����B���̂悤�ȃV�X�e�����w���G�n�x�ƌĂԂ��Ƃɂ���B��
�h���G�n�h�̃A�v���[�`�ł́A���z�I�Ȍ`��`���Ă����֓����̂łȂ��A�V�X�e���S�̂����̍\���v�f�Ƒ��݂ɍ�p�������āA�V�X�e���S�̂ƍ\���v�f����ɕω�������̂��Ƒ�����B�g�D�ł����A�l�����郋�[���œ��������ʂ��g�D�S�̂̏�Ԃɉe����^���A���ꂪ�g�D��ς��A����ɉe������Čl�̃��[�����ς��B
�g�D�ƌl�̊W�͑g�D�ƃ`�[���̊W�ɂȂ邱�Ƃ����邵�A�`�[���ƌl�̊Ԃɂ����̑��݊W���N���邾�낤�B�����l����ƁA�܂��Ɂh���G�ȁh�V�X�e�����B���G�ł��邪�A���G�ł��邪�䂦�ɃG�l���M�[�����܂ꂻ�����B�g�D���h�ÓI�ȁh�V�X�e���łȂ��A�h���I�ȁh�V�X�e���Ƒ����邱�ƂŁA�g�D�}�l�W�����g�̎����ω�����B
�w���G�n����x�ł́A�����Ĉȉ��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
��������]�A�Љ�̂悤�ȁw���G�n�x�͕������ė������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�w���G�n�x�̍\���v�f�̋@�\�E�U�����͑S�̂̕����̒��Ō��肳��邩��ł���B�@�B�̏ꍇ�ɂ́A�e���i�͂��ꂼ�ꌈ�܂����@�\�������Ă���B�@�B�������Ƃ��Ă��A���ꂼ��̕��i�̎����Ă���@�\�͕ς��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�u�����Ă���v�V�X�e���̏ꍇ�A�����ɂ���Ċe�\���v�f�̋@�\���̂����߂��Ă���B��
�L�����Łh�����h�ׂ�Ɓu�����ł̌�̈Ӗ��̑����������B���͂̒��ł̕��ƕ��Ƃ̑����������B��g�I�ɁA�ؓ��E�w�i�Ȃǂ̈ӂɂ��g���B�v�Ƃ���B���̎��X�ŕω�����g�D�̕����𑨂������邱�Ƃ��d�v�Ƃ�����B���[���őg�D������̂ł͂Ȃ��A�h�����Ă���h�g�D�����[��������Ƃ����t�]�̔��z���˔j���ɂȂ�B
����͕��G�n�̑g�D�}�l�W�����g�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N11��17���n
�@�@�@�@�@
�w�g�D�}�l�W�����g�̉Ȋw�ƐS�i��j�x�@�ivol.26�j
�u�Q�P���I�͋C�����c�Ƃ̎���ł͂���܂���B�v�u�����B�v�u�͂�Ԃ��������n���ɋA�҂������Ƃ����A�Ȋw�I�ȉc�Ƃ̎���ł��B�v�u�͂�Ԃ��W�Ȃ�������B�v�u�����A���Ђ̉c�ƃn�C�p�t�H�[�}�[�̍s���͂��܂����B�v�u�����B�v�u���̌��ʁA�K��p�x�ƑΉ��X�s�[�h������ɔ�Ⴗ��Ƃ̉�����������܂����B�v
�u�c�ƃ}���̊F����A��������P���P�ʂōs�������ɋL�^���Ă��������B�v�u�������B�v�u�������{�����ǂ����m���߂邽�߂̎����ł��B�v�u�܂��A���ꂪ�Ȋw�I�ȕ��@���B�v�u����ɋ��U�L�ڂ���������]���������܂��B�v�u�ǂ����B�v�u���T���ʂ͂��ĉ��P���@���w�����܂��B�v�u�ǂ��܂ŊǗ���������˂�B�v
�u���`�A�Ȋw�I�ȉc�Ƃ��n�߂Ĕ��N���o���܂����B�v�u�͂��B�v�u���̌��ʂ́B�v�u���̌��ʂ́B�v�u���������������Ƃ��ؖ�����܂����B�v�u������ꂽ�B�i�S�̐��j�v�u�c�ƃ}���̍s���Ǘ�������������āA����{����ڎw���܂��B�v�u���������{�b�g����Ȃ����B�i�S�̐��j�v�u�Ȋw�I�c�Ƃœ��{���ڎw���܂��傤�B�v
���яG�Y�͊w�������̍u���ʼnȊw�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
�����ł��Ȋw�́A���ƕ��Ƃ̈��ʊW�A���R�͂ǂ������ӂ��ɓ����Ă��邩�Ƃ������ʊW��ڎw���Ă�����̂ł��B�Ȋw�͖l��̐����o����ڎw���Ă���̂ł͂Ȃ��B�l�����������ɂ����Ăǂ������ӂ��ɔ\���I�ɍs�����ׂ����A����������ڎw���Ă��邾�����B���������Ӗ��ŁA�Ȋw�͔F���ł͂���܂���B��
��Ƃ̑g�D�}�l�W�����g�́A���̌��ʂƂ��ė��v�ݏo�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B���v�i����j�ƌv�ʂł���c�ƃ}���̍s���̈��ʊW���Ȋw�I�ɕ��͂���A�Ȋw�I�Ȏ��_�ɂ����āA�s���Ɣ���̊W�������Ă���B������グ�邽�߂ɁA�ǂ��\���I�ɍs������悢�����������Ă���B�������A�Ȋw�I�ȕ��@�͈̔͂̒��ŁB
���яG�Y�͊w�������̍u���ʼnȊw�ɂ��đ����Ă��������Ă��܂��B
���Ȋw�͂����������̂��ƁA���̐�����m���ĉȊw�����Ȃ����Ƃ������Ƃł��B���́A�Ȋw�����Ȃ���A�N�������Ă����܂���B���̖@����m�邱�Ƃ����āA�l�Ԃɂ͑�Ȃ��Ƃł��B�Ȋw�͖{���ɕ���m�铹�ł͂Ȃ��A�����ɔ\���I�ɐ������ׂ����A�s�����ׂ����A���������֗��Ȗ@�������o���w��Ȃ̂ł��B����������ւ�K�v�Ȃ��Ƃ�����ǂ��A�����ƁA�Ȋw��������Ă���Ζl��͕���m�邱�Ƃ��ł���Ǝv���Ă��܂��B��
�g�D�}�l�W�����g�̖@�����Ȋw�I�ȕ��@�Ŕ������邱�Ƃ́A���v�Ƃ������ʂ��o�����߂ɏd�v���K�v�ȃv���Z�X���B�Ȋw�I�Ȏ��_����Ȃ���ΐ��_�_�ɂȂ��Ă��܂��B�������A�Ȋw�I�ȕ��@�őg�D�}�l�W�����g�̖@�����킩�����Ƃ��Ă��A����őg�D�}�l�W�����g���킩�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���ꂾ���ł͂��܂������Ȃ��B
��Ƃ̑g�D�}�l�W�����g���l���邤���ŁA�}�b�L���[�[�̂VS�Ƃ����t���[�����[�N�i�v�l�̘g�g�݁j������B�������G�Ȃ̂ł��܂���p����Ȃ����A�g�D�}�l�W�����g�̉Ȋw�ƐS�̑S�̑������܂��\���Ă���B�n�[�h�̂RS�ƃ\�t�g�̂SS�A�V��S�����܂��W�Â��āA�ЂƂ̗L�@�̂Ƃ��đg�D���@�\������B
�n�[�h�̂RS�́ASrategy�i�헪�j�AStructure�i�g�D�\���j�ASystem�i���x�j�B�\�t�g�̂SS�́AShared value�i���ʂ̉��l�ρj�AStyle�i�g�D�����j�AStaff�i�l�ށj�ASkill�i�X�L���j�B�Ȋw�I�ȕ��@�Ŗ@�����ł���̂́A�n�[�h�̂RS�͈̔͂��낤�B�g�D�}�l�W�����g���@�\������ɂ́A�ʂɃ\�t�g�̂SS���K�v���B
�VS�̊T�O�}�́A�^��Shared value�i���ʂ̉��l�ρj�������āA���̂US�����̎�����͂݁A�Ԃ̖ڏ�ɂ��ׂĂ��Ȃ����Ă���BShared
value�i���ʂ̉��l�ρj�͂VS�̒��S�ɂ����āA���̂US�̌���ɂȂ���̂��B�t���[�����[�N�͊�Ƃ̐�������͂������́B���������g�D�̒��ɂ͑S�ċ��ʂ̉��l�ς��������B
Shared value�i���ʂ̉��l�ρj�AStyle�i�g�D�����j�AStaff�i�l�ށj�ASkill�i�X�L���j�́A�m���̎��i�����I�ȃX�L���������A��������v�ʂ�������낤�B�g�D�}�l�W�����g�̒��ŁA�Ȋw�I�ȕ��@�����ɗ����Ȃ��͈͂�\���Ă���B�Ȋw�I�ȕ��@���y�Ȃ�����ɂ��āA�Ȋw�قǖ����ȉ�������l�͂܂��������Ă��Ȃ��B
�g�D�}�l�W�����g�̐S�͈̔͂ɂ��ẮA���ɂ�����������g���Đ�����������Ƃ��������A���������̂��̂������悤�Ƃ���w�͂��K�v�ɂȂ�B�������͂��ꂼ��̑g�D���ƂɈႤ�B�Ȋw�I�ȕ��@�����܂��g���ăn�[�h�̂RS���\�z���A�\�t�g�̂SS�ł��̕��ɍ��𒍓�����B�Ȋw�ƐS���g�D�}�l�W�����g�̋쓮�͂ƂȂ�B
����̓��[���ƃV�X�e���_�C�i�~�N�X�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N11��4���n
�@�@�@�@�@
�w�g�D�}�l�W�����g�̉Ȋw�ƐS�i�O�j�x�@�ivol.25�j
�u�����͉䂪�Ђ̉c�ƕ��Ɋ������邽�߂ɁA�A�j�}���l����������Ăт��Ă��܂��B�v�u�c�ƃ}���̊F����A�C�������A�C�������A�C�������A�C�������`�A�������������B�v�u���肪�Ƃ��������܂����B�v�u�킠�`�A�͂��A�͂��B�v�u����ł͂Ƃ��ƂƂ��A�肭�������B�v�u�����̉�Ђǂ��ɋ������Ƃ��A�{�P�B�i�S�̐��j�v
�u�Ƃ������Ƃō��N���C�����ōs�����`�B�v�u���`�A���ĉ�������Ȃ������B�v�u�ǂ����A�ǂ����B�v�u�C��������`���B�v�u���́`�A���̎���͋C�������ᔄ���ł���B�v�u�ȂƁB�v�u�Ȋw�I�ȉc�Ƃ�����ׂ��ł���B�v�u�Ȋw�I���Ăǂ������I��B�v�u���錻�ۂƂ��錻�ۂ̊ԂɈ��̖@���������邱�Ƃł���B�v
�u���`��A����łǂ�����Č�����B�v�u�Ȋw�I�ȕ��@���g���Č������ł��B�v�u�Ȋw�I�Ƃ͕��@�̂��ƂȂ̂��B�v�u�܂��ŏ��ɁA����@�������藧�Ƃ��������𗧂Ă܂��B�v�u�ӂށB�v�u�����ʼn��x���������ē������ʂ��o��A����͉Ȋw�I�ɍł������������Ƃ���Ƃ������@�ł��B�v�u�Ȋw�Ƃ͕��@�Ȃ̂��ȁB�v
�u�Ȋw�ɂ́h���؎�`�h�Ƃ����l����������܂��B�v�u�ӂ��B�v�u������ϑ��ɂ���Ĕ������\�����Ȃ���A���̖@���͉Ȋw�I�Ƃ����Ȃ��B�v�u�ق��B�v�u�P�O�O�O�����ʂ��o�Ă��A�P�O�O�P��ڂɈႤ���ʂ��o�Ȃ��ƌ�������Ȃ��B�v�u����B�v�u������A�^�����ƌ�����������Ȋw�I�ȕ��@�Ƃ͂����Ȃ��B�v
�Ȋw�I�Ƃ́A�^���ɋ߂Â����߂̂ЂƂ̕��@�̂��Ƃ��B�Ȋw�I�ɐ^���ł���Ƃ������Ƃ́A�Ȋw�̕��@�ɂ��Ό��ݍł��^���ɋ߂������ł���Ƃ������ƁB�F���͂P�R�V���N�O�Ƀr�b�N�o���őn��ꂽ�B�������̉\�������邩��A���݁A�Ȋw�I�ɐ^���ł���B�_���F����n�����́A���̉\���͂Ȃ�����Ȋw�I�ł͂Ȃ��B
�u�h���q�l�ɒ��J�ɐڂ���Δ��オ������h�Ƃ����@���������Ƃ��āA���x����������ΉȊw�I�ȕ��@�ɂȂ�H�v�u�Ȋw�͌v�ʂł�����̓��m�̊W���݂܂��B�v�u�������ɁA���J���͌v�ʂł��Ȃ��ȁB�v�u�h���q�l�ւ̖K���������Δ��オ�オ��h�͉Ȋw�I�Ɍ����ł��܂��B�v�u�Ȋw�I�Ƃ͌v�ʂł��錻�ۂ�Ώۂɂ��邱�Ƃ��B�v
���яG�Y�͊w�������̍u���ʼnȊw�̖@���ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���ߑ�Ȋw�Ƃ������̖̂@�����`����A����͈�̌v�ʂł���ω��ƁA������̌v�ʂł���ω��Ƃ̊Ԃ̃R���X�^���g�ȊW�Ƃ������Ƃł��B�Ȋw�͂��ł��A���̖@���̉��ɂ���̂ł��B�Ȋw�͖@���ɏ]���o�������ɁA�l�Ԃ̌o�������߂��̂ł��B�����������Ƃ����N�͂͂�����ƒm���Ă��Ȃ���Αʖڂł��B��
�������͉Ȋw�I�ɐ^�����ƌ�����ƁA���ꂪ�^�����Ǝv���������B�F���͉Ȋw�I�ɂP�R�V���N�O�Ƀr�b�O�o���őn��ꂽ�ƌ�����ƁA���ꂪ�^���ł������Ǝv�����݂����ɂȂ�B�������A���ꂪ���̂Ƃ���ł��m���炵���^���Ƃ��āA�v�ʂł���@����T���Ȃ���A�V���Ȑ^���i���j���l��������̂��Ȋw�I�ȕ��@���B
�g�D�}�l�W�����g���Ȋw�I�ɍs���Ƃ́A�v�ʂł���Q�̌��ۂ����߂āA���̊Ԃ̖@�����ɂ��ĉ���������A�������J��Ԃ��Ă������Ƃ��B�������J��Ԃ��āA�����̐��x���グ��B���̂��߂ɂ́A�܂�����������Ȃ���Ύn�܂�Ȃ��B���^���ɋ߂������ɂ��邽�߂ɂ́A�ł��邩����_���I�ɉ��������肠����B
���яG�Y�͓����u���ʼnȊw�̕��@�ɂ��đ����Ă��������Ă��܂��B
���Ȋw�ł͌v�Z�Ƃ������Ƃ���ԑ厖�Ȃ��Ƃ�����A�P�V���I�ȗ��Ȋw���ł��������̂͐��_�̖��A�S�̖�肾�����̂ł��B���_�Ƃ������̂͌v��Ȃ����낤�B�Ȋw�͌N�̔߂��݂��v�Z���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B��
�g�D�}�l�W�����g�́A���_�_�����Ȋw�I�ɍs����ׂ����낤�B���̎���A�Ȋw�I�ȕ��@���������͂������A���ʂ��オ����@�͑��ɂȂ��������B�������A�����ł͐l�Ԃ̐S�̖�肪�ΏۊO�ł��邱�Ƃ�Y�ꂪ�����B�@�B�I�ɐl�Ԃ𑨂������ɂȂ�B�Ȋw�I�ȃ}�l�W�����g�̊O���ɁA�l�̐S�����邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����͈��������}�l�W�����g�̉Ȋw�ƐS�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N10��20���n
�@�@�@�@�@
�w�l���َ̈�i���Z�ƈӎv����i��j�x�@�ivol.24�j
�u�݂�Ȃ������A�ӌ����Ԃ������B�v�u�����A�ӌ��َ̈�i���Z�ł��ˁB�v�u�������A�h��ɂ��������Ă������B�v�u�����̃e�[�}�́h�Z�[���X���{�����[�V�������h�B�v�u�܂�A�c�Ɗv���ł��ˁB�v�u�������A���܂ł̂����ł̓W���n���B�v�u��[���A�v�����N�������Ⴄ���[�B�v�u�S���O���������A�t�@�C�g�I�v
�u�Ђ��[���烍�[�����O���A���̂��[�B�v�u���[�����O�Ȃ��Ԃ̖��ʂ��A�����[�B�v�u�ڋq��I��Œ�ĉc�Ƃ��A�܂��������B�v�u���₢��A�r�m�r�ōL���ł����Ⴄ��B�v�u�����͑�Z�̃e���r�b�l�łǂ����B�v�u�ȂɌ����Ă�́A�܂��͊����q�ɘb����ł���B�v�u���������Ă����荞�܂Ȃ��A�Ă̂͂ǂ����B�v
�u���`��A�ȂႤ�ȁB�v�u���`�A�������K���œ����Ă܂���B�v�u����͂킩����ǂˁB�v�u���Ⴀ�A�����Ⴄ���B�v�u�����ˁA�i���Z���Ă����X��̃P���J�ɋ߂��̂ˁB�v�u�͂��B�v�u�܂�A���[�����Ȃ��������肪�|���܂őł������Ă��邾���Ƃ������B�v�u�������ɁA�i���Z�őg��ł��銴���͂Ȃ��ȁB�v
�����ӌ����Ԃ����������ł́A�َ�i���Z�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ӌ��ƈꌾ�Ō����Ă��A���̓��e�ɂ̓��x��������B�P�Ȃ�ӌ����A�l���������l�����B�P�Ȃ�ӌ��Ƃ́A���̏�Ŏv�������ӌ���A�}�X�R�~�ȂǑ��l�̈ӌ��ɉe������Ă����v������ł���ӌ����B�܂�A�����ōl���ē����ӌ��ł͂Ȃ��B
����l�����Ă��Ȃ��ӌ��́A�ӌ����̂��̂��ア�B�ア���قǂ悭�i����B�������ア�Ɩ��ӎ��ŕ������Ă��邩��A��ɑ�����U�����Ď����͋����Ǝ����Ɏv�����܂���B�U������߂��玩���������B���肪������߂�܂Ŗi��������B�i���Z�����藧���߂ɂ́A������x�Γ��ȃ��x���̋Z�p�Ƌ������K�v���B
�ӌ��������Ƃ́A���ꂪ����l��������Ă��邱�Ƃ��B�ӌ��́A������O�������t�ł�����B���S�X�ilogos�j�Ƃ����M���V���ꂪ����B�L�����ɂ��A�@�T�O�E�Ӗ��E�_���E�����E���R�E���_�E�v�z�Ȃǂ̈ӁB�A����B�����B�Ƃ���B�Ñ�M���V������ɂ́A���t�Ƙ_���Ƃ͓������Ƃł������B
���Ƃ����ǂ�Ό��t�Ƃ͘_���ł���A���t�����邩��_��������B�l�Ԃ͌��t��b���ȏ�A�_�����瓦����Ȃ��B���t�̈Ӗ���������Ƃ��A���ɕ����̒P�ꂪ�Ȃ��镶�͂̏ꍇ�́A���ʂ��Ă��遁�_���I�ł��銴��������B�Ӗ���������Ȃ���A���t�͂����̋L���̗��B�m��Ȃ��O����̏ꍇ�������Ȃ�B
�����̈ӌ��M���Ă�����ɈӖ����`���Ȃ���A�Γ��ȑΘb�͂ł��Ȃ��B���t���s�������Ă��Ă��A�Ӗ����s�������Ă��Ȃ���ΑΘb�ɂȂ�Ȃ��B�Ӗ��̂Ȃ����t�̋L�����s�����������ŁA���݂��Ɉ���ʍs�̕��������Ă���悤�Ȃ��̂��B�قȂ�l���m�̑Θb���َ�i���Z�́A���̘b�����t�̈Ӗ�����ɂȂ�B
���t���L�����ĈӖ��ɂȂ�Ƃ��A���t�́h���t���_���h�̃��S�X��ԂɂȂ�B�_���I�ł��遁���W�J���ł���Ƃ́A���ʁi�����ƌ��ʁj�W�����m�ł��邱�Ƃ��B�u�Ȃ�����������̂��v�u���������Ăǂ��Ȃ�̂��v�Ƃ����Q�̖₢�ɂǂ��܂œ������邩�B���̖₢�Ɠ���������J��Ԃ����Ƃ��h�l����h���Ƃ��B
���������M���悤�Ƃ���ӌ��ɂ��āA�_���I�ƌ�����܂Ŏ���l�������Ă����B�����̈ӌ��������l���ɂ܂ň�ĂĂ����B����������Ζi����K�v�͂Ȃ��B�����ōl�������Ă��邩��A���肪�ǂ��l����Ă��邩���C�ɂȂ��Ă���B�l���̂Ԃ��荇���ɂȂ�Θ_�������[���ɂȂ�A�َ�i���Z���������Ƃ��ł���B
�ӎv����̂��߂ɏd�v�ȍl���َ̈�i���Z�́A�o�ꂷ��I��̃g���[�j���O�̎��Ɨʂɍ��E�����̂��B�~�[�e�B���O�ɏo�Ȃ��郁���o�[���A�ݒ肳�ꂽ�e�[�}�ɑ��鎩���̈ӌ��ɂ��čl�������āA�ӌ��Ƃ��������l���ɏ�������B�������O�ɑS���g���[�j���O���Ă��Ȃ������ꍇ�́A�댯������J�Ò��~�ɂ���B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŋc�_�̕��@�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
��������������ςɂƂ���Ȃ����߂ɂ́A�Η����邢�����̈ӌ��ɂ��ċc�_���A�_�����L���A�O��I�ɍl������ق��͂Ȃ��B��
�h�Η����邢�����̈ӌ��ɂ��ċc�_���A�_�����L���A�O��I�ɍl����h���߂ɂ́A���O�Ɏ����̈ӌ��ɂ��āh�_�����L���A�O��I�ɍl���h�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������O�����A�i���Z�̃S���O�����Ă���g���[�j���O���鎞�ԂȂǂȂ��B�������A���t�̊i���Z�̏ꍇ�́A���̓�����O����������Y��Ă��܂��̂��B
����̓}�l�W�����g�̉Ȋw�ƐS�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N10��1���n
�@�@�@�@�@
�w�l���َ̈�i���Z�ƈӎv����i�O�j�x�@�ivol.23�j
�u���̐����������Ԕ��オ��������ł���ȁB�v�u�\����܂���B�v�u���Ȃ����Ȃ�T���ł��ł����B�ǂ����邩�l����A�l����́B�v�u�͂��A�ڋq�j�[�Y��c�����邽�߂̏����W�����܂��B�v�u����Ȏ��Ԃ͂Ȃ���A�Ȃ��B�v�u�������Ђ̓����͂��ē��Ђ̐헪���l���܂��B�v�u����Ȑ��_�͂���Ȃ���B�v
�u�����ƍl���Ă���z�͂��Ȃ��̂��B�v�u���`�A���܂Ŕ��ꂽ�����ɉ������Ă������������܂��B�v�u���A�Ⴄ�ł���B�v�u���A���݂܂���B�v�u���̒��N�̌o�����猾���Γ����͕������Ă��B�v�u�����Ă��������B�v�u�����炳�`�A����ȂƂ��͋C���������Ȃ����B�V���v���ɍl���Ȃ�����B�v�u���̂Ƃ���B�B�v
�}�l�W���[�́h�_�[�X�x�C�_�[���h���Ă���B�V�l����͂����Ƒf���ȋC�����ŁA���ł��z�����悤�Ƃ��Ă����͂����B�ǂ����ŊԈ���ă_�[�N�T�C�h�ɗ����Ă��܂����B�������͎̂����ŁA�Ԉ���Ă���̂͑��l���B�Ȃ�ł���ȊȒP�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��̂��B������܂ŋ������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�}�l�W���[�͂炢��B
�}�l�W���[�͕�������Ă悤�ƁA����̒��N�̌o���Ɋ�Â����c�Ǝ�@��M�����Ȃ��狳�����B���J�����o���A���オ�オ��C�z�͂Ȃ��B�c�Ɖ�c�Ń}�l�W���[�������ɍl�������߂Ă��A�N���ӌ�������Ȃ��Ȃ����B�������炷��h�����̈ӌ��h�������ΕK���ے肳��邩�炾�B�����āA��c����h�����̈ӌ��h���������B
�u����ȂɃ}�l�W���[�̉����撣���Ă�̂ɁA�Ȃ�ŒN�������l���ĂȂ��B�v�u�c�B�v�u���܂��ɐ�̐▽�̃s���`�Ȃ킯��A���ނ���݂�ȕK���ōl���Ă�B�v�u���́`�A�}�l�W���[�̌o������������������ł����B�v�u���̌o�����Ăǂ�����̂�A�����ōl���Ȃ�����B�v�u���`�A�_���������B�i�S�̐��j�v
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ňӎv����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���Η����邢�����̈ӌ����Ԃ������A�قȂ鎋�_����̑Θb���s���A���܂��܂Ȉӌ��̒�����ЂƂ�I�Ԃ��Ƃɂ���Ă����A���f�͓�����Ȃ��B�ӎv����̑�ꃋ�[���́A�ӌ��̈Ⴂ���Ȃ��Ƃ���ł͈ӎv����͂ł��Ȃ��A�Ƃ������̂��B��
�����͈ӌ�������Ȃ��A�����l���Ă��Ȃ��Ƌ�s��}�l�W���[�͏��Ȃ��Ȃ��B�����������͍ŏ�����ӌ�������Ȃ��������낤���A�����l���Ă��Ȃ��������낤���B����Ƃ������ɕω����������͂����B�}�l�W���[�Ɏ����̈ӌ����Ă��炦�Ȃ��Ɗm�M�����Ƃ����B���ꂪ���Ȃ̂������͒m���Ă���B�}�l�W���[���m��Ȃ��������B
�����͐������đ��l�͊Ԉ���Ă���A�Ǝv���͍̂l���Ă݂�Ε��ʂ̂��Ƃ��B���Ȃ��Ƃ������͐������Ǝv���Ȃ���A����������Ƃ��Ɏ��M�͐��܂�Ȃ��B�����͊Ԉ���Ă���Ǝv���ĉ��������邱�Ƃ����邾�낤���B�������������������Ǝv�����ނ��ƂƁA���������������ǂ����Ƃ������Ƃ͕ʂ̂��Ƃ��B�������낤���Ȃ�B
�����͐������Ǝv������ōs�����邪�A�{���ɐ������̂��낤���B������������Ԉ���Ă��邩������Ȃ��B�����Ɛ������l��������̂ł͂Ȃ����B�������o�ł��邩���A�낤�������z���錮�ƂȂ�B�܂��͎������g�����o�I�ɔ��Ȃł��邩�B���ꂪ�ł���A���l����������������Ȃ����Ԉ���Ă��邩������Ȃ��ƍl������B
��������������������Ȃ����Ԉ���Ă��邩������Ȃ��A��������������������Ȃ����Ԉ���Ă��邩������Ȃ��B�����}�l�W���[���C�Â����Ƃ��ł����Ƃ��A�c�Ɖ�c�ł̕����ւ̐ڂ����͂P�W�O�x�ς�邾�낤�B�����Ƃ͈Ⴄ�����̈ӌ��������ƕ��������Ȃ�B���܂ł̕����փC���C���́A�����̍l���ւ̋����֕ς��͂����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ňӎv����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���ӎv����ɏG�ł��l�́A�u����s���������������A���͂��ׂĊԈ���Ă���v�ȂǂƂ����O��o�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�u�����͐������A�ނ͊Ԉ���Ă���v�Ƃ������z�Ƃ������ł���B�ނ���A�Ȃ��l�ɂ���Ĉӌ����Ⴄ�̂��A���̗��R�������ɒT�낤�Ƃ���B��
�l�ɂ���Ĉӌ����Ⴄ�̂����ӎ��ŕ������Ă��邩��A���������̂��ʓ|�������āA�l�͑��l�̈ӌ������Ƃ��Ȃ��̂�������Ȃ��B�l���ꂼ�ꂪ�������Ǝv������ł���ӌ��̂Ԃ������́A�܂��ɍl���َ̈�i���Z���B�}�l�W���[�̖����́A�َ�i���Z���牿�l����ӎv�����n������v���f���[�T�[�ɂȂ邱�Ƃ��B
����͈��������}�l�W���[�̈ӎv����ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N9��16���n
�@�@�@�@�@
�w�R�~���j�P�[�V�����͉萶���邩�i��j�x�@�ivol.22�j
�u���Ђ̌o�c���O�́A���q�l�ɐS�n�悢��������邱�Ƃł��B�v�u�͂��͂��A�������������O���Ă܂���~�B�i�S�̐��j�v�u�ЂƂ�ł������̂��q�l�ɐS�n�悢��������邱�Ƃ����Ђ̎g���ł��B�v�u�����̒��щ��ɂ��悤���Ȃ��B�i�S�̐��j�v�u�S�n�悢�����Ƃ́A�P�����ƂɃX�g���X�����Z�b�g�����Ƃ����Ӗ��ł��B�v�u�����̓T�b�J�[�̎����ϐ킾�A�莞�ɋA�����Ⴄ��~�B�i�S�̐��j�v�u����ł͒���I���܂��B�v
�`�}�l�W���[�͎В�����u�o�c���O�ɂ��Ă����ƕ����ƃR�~���j�P�[�V���������B�v�ƌ����A�����̒���ŕ����Ɍo�c���O�̐��������Ă���B���������ɐ������Ă��邤���ɁA�}�l�W���[���o�c���O�̈Ӗ����D�ɗ����Ă����B�������A�����������̂��B�����ƃR�~���j�P�[�V����������Ă悩�����B�������S���痝�����Ă���͂����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Œm�o�ƊT�O�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���l�Ԃ��������w�K����ۂɂ́A�m�o�ƊT�O�͕��������������т��Ă���B�T�O�Ȃ����Ēm�o�͐��藧�����A�m�o�Ȃ����ĊT�O�͐��藧���Ȃ��̂ł���B�肪�m�o�ł��Ȃ��Ȃ�A�܂��̒m�o�͈͂ɓ����Ă��Ȃ��Ȃ�A���̒��g���R�~���j�P�[�V��������͕̂s�\�ł���B��
�����ɂ́h�o�c���O�h�Ƃ����T�O���m�o�ł��Ă��Ȃ��B�o-�c-��-�O�Ƃ����S������������Ƃ��ăC���v�b�g����邪�A�����ɈӖ��͔���Ȃ��B�O��̃R�����ŁA�R�~���j�P�[�V�����Ƃ͌��t�̈Ӗ������L���邱�Ƃ��ƒ�`�����B���t�̈Ӗ������L���邽�߂ɂ́A���̑O��Ƃ��Č��t�̊T�O�����L���Ă���K�v������B
�h�o�c���O�h�̂悤�ɒ��ۓx���������t�́A���ɒ��ӂ���K�v������B���t���̂��̂̓V���v���Ȃ��߂ɁA��������Ȏv�����݂ŊT�O���������₷���B���݂̑ҋ��ɕs���������Ă���Ј��́A��������ڂ���炷���߂̕��ւ��Ǝv������ł��邩������Ȃ��B�����ɉ��x�o�c���O�̐��������Ă��A�{���I�ȈӖ��͓͂��Ȃ��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ŋ��҂ƒm�o�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���킽�������͌����Ƃ��āA���������҂��鎖�������m�o���Ȃ��B�����ނˁA���������Ƃ����āA�����������Ƃ��̂��B���ҊO�̎����͂قƂ�ǂ܂������Ƃ߂��Ȃ��B�ڂ⎨�ɓ������Ƃ��Ă����������B���邢�́A���҂ǂ���̓��e���ƌ�����Ƃߕ��������̂��B�l�Ԃ̐S�́A����������ۂ�h�����A���҂Ƃ����g�g�݂ɂ͂ߍ������Ƃ���̂��B��
����́u�肢�͂Ȃ�������̂��H�v�̓����ɋ��ʂ�����̂�����B�肢�t�͓�������͂�����܂߂Ă�������̘b��������A���k�҂͎��������҂���b���������Ă��Ȃ��B������A�肢�͕K��������B�������A����Ō��C���o��̂��肢�̖{���ł����āA������͂��ꂪ�{���ł͂Ȃ��̂��낤�B���������C�����炢�ɐ肢�t�̂��ƂցB
���k�҂Ɛ肢�t�̊Ԃɂ͎��̂̃R�~���j�P�[�V���������藧���Ă���B���鑊�k�҂��Ђ����ɂ���肢�t�́A�����ɂƂ��ē����肪�����肢�t���낤�B�����肪�����Ƃ������Ƃ́A���k�҂��������҂��Ă��邩�z������\�͂������Ƃ������Ƃ��B�肢���Ĕ[�����銴�o�́A�R�~���j�P�[�V���������̃q���g�ɂȂ�B
�肢�́A��ɑ��k�҂���R�~���j�P�[�V�������X�^�[�g����B�ŏ��ɑ��k�҂̊��҂���n�܂邩��A�肢�t�͂��̊��҂����Ƃ����s�ׂ��\�ɂȂ�B�肢�Ɋ��҂������Ȃ��l�ɂ́A�ǂ�Ȃɑf���炵���肢�����Ă���������邾�낤�B�o�c���O�Ɋ��҂̂Ȃ������ɔM���ۂ��o�c���O��������Ă��A�����o�̂܂ܖ�������Ă��܂��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŏ�Ӊ��B�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
����Ӊ��B�ɂ���ē`������̂́A���߁A���Ȃ킿���炩���ߌ��߂�ꂽ���}�����ł���B���`�x�[�V�����͌����ɋy���A�����ɂ�����鎖���́A�g�b�v�_�E���ɂ���Ă͌����ē`�����Ȃ��B���̂悤�ȓ��e��`���邽�߂ɂ́A�m�o���鑤����m�o��U�����Ƃ��鑤�ւ́A�{�g���A�b�v�^�̃R�~���j�P�[�V���������߂���B��
�o�c���O�̈Ӗ���`�������Ȃ�A�܂��ŏ��ɕ����ɖ₢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�N�͓��Ђ̌o�c���O�ɂ��Ăǂ��v�����H�v�A�u���Ђ̌o�c���O�͂ǂ�Ȃ��Ƃ����������̂��Ǝv�����H�v�A�u�N�����Ђ̌o�c�҂�������ǂ�Ȍo�c���O���ӂ��킵���Ǝv�����H�v�c�B�{�g���A�b�v�̎��₩��A�R�~���j�P�[�V�������ٓ����͂��߂�B
����̓}�l�W���[�̈ӎv����ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N9��1���n
�@�@�@�@�@
�w�R�~���j�P�[�V�����͉萶���邩�i�O�j�x�@�ivol.21�j
�u�`�}�l�W���[�A�����ƃR�~���j�P�[�V����������Ă���̂��H�v�u�����A�ŋ߂͎�肷�����Ȃ��Ă������炢�ł���B�v�u�ǂ�ȕ��Ɏ���Ă���H�v�u�Ƃɂ����c�Ƃ͔M���v���łԂ���I�ƂP���P�O��̓����o�[�Ɍ����Ă��܂���B�v�u����ŕ����͉��Č����Ă���H�v�u�撣��܂��I�ƕb���ŕԂ��Ă���܂���B�v
�R�~���j�P�[�V���������Ƃ������Ƃ́A�\�ʓI�ɂ͎��������đ��肪���Ă��݂��Ɍ��t�����킷���ƂɈႢ�Ȃ��B�������A���̓�l�������ʼn������Ă��邩�͖ڂɌ����Ȃ��B�ڂɌ����Ȃ����Ƃ��������͓̂���B����ł́h�R�~���j�P�[�V����������Ă����ԁh�Ƃ́A��l�̊Ԃʼn����s����Ƃ��̂��Ƃ������̂��낤���B
��l�̊ԂɌ��t�����킳��邱�Ƃ�\������p�P��͏��Ȃ��Ȃ��Btalk�i�b�������A���k�j�Aconversation�i��b�A�Βk�j�Achat�i������ׂ�j�Agossip�i���킳�b�j�Adialogue�i�Θb�j�Adiscussion�i���c�A�c�_�j�Adebate�i���_�A�c�_�j�Aargument�i�c�_�A���_�j�A������communication�i�`�B�A�ӎv�a�ʁj�B
communication�ȊO�̒P��́A��l�̊Ԃ̕��͋C���Ȃ�ƂȂ��C���[�W�ł���B�������Acommunication�����͂��̏�̕��͋C���C���[�W���ɂ����Bcommunication�Ƃ����T�O�́A����ȊO�̒P����ЂƂ��̊K�w�ɂ��邢���OS�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B�Ⴆ�Acommunication���@�\����������talk�����Ă���Ƃ������ɁB
�W�[�j�A�X�p�a���T�ɂ��Acommunicate�̌��`�́h���l�Ƌ��L����h���Ƃ��B�Ȃ�R�~���j�P�[�V���������Ƃ́A�����Ƒ��肪���t�����L���邱�Ƃ��낤�B����Ɍ����A���t�̈Ӗ������L���邱�Ƃ��B�u�R�~���j�P�[�V����������Ă��邩�H�v�́A�u����ƌ��t�̈Ӗ������L���Ă��邩�H�v�ƌ�����������Ƃ������Ƃ��B
������Ɛ��Ԃ����n���Ă݂�A���݂��Ɍ��t�̈Ӗ������L����Ȃ��܂܉i���Ɖ�b�������Ă����ʂ����邱�Ƃ��ł���B�����ɉ�b�����肵�Ȃ����b�������Ă����Ƃ�����ʂ�����ƁA�R�~���j�P�[�V�������������i�_�Ɓj�Ǝv���邱�Ƃ�����B�����ł͉�b�͐������Ă��邪�A�R�~���j�P�[�V�����͐������Ă��Ȃ��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŃR�~���j�P�[�V�����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���R�~���j�P�[�V�����̎�͎̂�ł���B������h���M�ҁh�̓R�~���j�P�[�V���������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�������t���邾���Ȃ̂��B�N�ɂ������Ă��炦�Ȃ��Ȃ�R�~���j�P�[�V�����͐��藧�����A���M�҂����ɂ������t�������̎G���ɂ����Ȃ��B��
�R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����́A���M�҂���̂łȂ��A�肪��̂ł��邩�ǂ����ɂ������Ă���B�������A�R�~���j�P�[�V��������낤�Ƃ��鑤�͔��M�҂ł��邱�Ƃ��قƂ�ǂ�����A�i���M�҂ł���j�������ǂ����邩���l���ĂĂ��܂��B�{���́A��̂��Ƃ�z�����邱�Ƃ���n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ł���ɂ��������Ă��܂��B
������A�܂��̌��t���g��Ȃ�������A�R�~���j�P�[�V�������͐��藧���Ȃ��B���������̌��t�́A�o���ɍ����������̂łȂ��Ă͂����Ȃ��B���̂��߁A���t�̈Ӗ���l�X�ɐ�������͖̂��ʂȎ��݂ł���B�o���ɍ������Ă��Ȃ����t�͎Ƃ߂悤���Ȃ��B��
�R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ́A������̂���߂Ď��̂Ɉӎ����t�]�����A�����̌��t�łȂ���̌��t���g�����Ƃ���͂��܂�B�R�~���j�P�[�V�����Ƃ̓}�[�P�e�B���O�Ȃ̂ł������B�}�l�W���[�Ȃ�Ε����̗���ōl���A�����̌��t�Ō��B���������i��j�Ɋ�����ꂽ�Ƃ��A�R�~���j�P�[�V�������萶���͂��߂�B
����͈��������}�l�W���[�ƃR�~���j�P�[�V�����ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N8��19���n
�@�@�@�@�@
�w���[�_�[�V�b�v�͔����ł�����̂��x�@�ivol.20�j
�u�`�}�l�W���[�A������Ƃ������ȁB�v�u�͂��B�v�u���̂Ƃ���N�̃`�[���͌��C���Ȃ����A���т������Ă��邶��Ȃ����B�v�u���A���̒ʂ�ł��B�v�u�����ƃ��[�_�[�V�b�v�����Ă����Ȃ��ƍ����B�v�u�撣���Ă������ł����B�v�u���肶��_���Ȃ́A������x�����Ă����Ǝ��H���Ȃ����B�v�u�́A�������܂����B�v
�u���[�_�[�V�b�v��������āA�悭�l����Ɖ��������炢���̂��킩��Ȃ��ȁB�v�u�����܂���A���[�_�[�V�b�v�̖{�͂ǂ��ł����H�v�u������ł��B�v�u����A����Ȃɂ���̂��B�v�u�����B���������w�T���ł��킩�郊�[�_�[�V�b�v�x����Ńo�b�`�����B�v�u�ǂ�ǂ�A�������ɂ킩��₷�����B���[�_�[�V�b�v�ȒP�����B�v
�u������Ƃ����A�ŋ߂̂`�}�l�W���[�������ˁB�v�u����A�����ƃr�W�����A�r�W�������Ă��邳�����A�₽��ƃn�C�e���V�����Ȃ�ˁB�v�u�K�v�ȏ�ɂ܂Ƃ����Ă��邵�A�ق��Ƃ��Ă��Ċ����B�v�u�ȂςȖ{�ł��ǂ�������Ȃ��B�v�u���s����̍D�������A�e������₷�����i������ȁB�v�u�͂��B�v
�u�`�}�l�W���[�A������Ƃ������ˁB�v�u�͂��B�v�u���[�_�[�V�b�v�����Ă���̂��B�v�u�����A�`�[���̃r�W������`���āA�`�[���̖ڕW�������āA�����o�[�Ɏx���I�Ɋւ���Ă���̂ŁA�����ɋ߂��͂��ł��B�v�u�ӂށA�������`�[���̊��C�͂���ɗ����Ă��邼�B�v�u����Ȃ͂��́B�v�u���[�_�[�V�b�v���������蔭�������B�v
�Ȃ����[�_�[�V�b�v�̋��ȏ��ǂ���ɁA���[�_�[�V�b�v�ɕK�v�ȏ��������s���Ă���̂ɁA�S�����ʂ��Ȃ��̂��B����ɂ͋t���ʂɂȂ��Ă��܂��̂��B����̓��[�_�[�V�b�v�Ɋւ��ď����ꂽ���̂��A���͓I�ɏ����ꂽ���̂����Ȃ����炾�낤�B�ŏ��Ƀ��[�_�[�V�b�v���������ꂽ��Ԃ������āA���̏�������t���ŕ��͂��Ă���B
���[�_�[�V�b�v�����Ă��郊�[�_�[�́A�r�W���������A�ڕW�������A�����o�[�Ɏx���I�Ɋւ���Ă��邩������Ȃ��B����������́A���[�_�[�V�b�v�����Ă���Ƃ����S�̂���ɍ����āA�������̓I�ȍs���Ƃ��������ɕ������Ă���B�זE���W�߂Ă��l�Ԃ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂Ɠ����ŁA��������S�̂����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
���͓I�ɂ킩������̓I�ȍs����ςݏd�˂������ł́A���[�_�[�V�b�v�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���������ۂɋ�̓I�ȍs�����Ȃ���A���[�_�[�V�b�v�͎������Ȃ����낤�B���̑S�̂ƕ����̒f��́A�ǂ���������z������̂��B���[�_�[�V�b�v�́h��������h�̂łȂ��A�h���������h�ƍl������ǂ����낤���B
���[�_�[�V�b�v����������Ă���Ƃ��́A�����o�[���N���疽�߂���邱�ƂȂ��A�������烊�[�_�[�ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���B���[�_�[���猩��ƁA���[�_�[�V�b�v�̔����͎g���B�����o�[�����[�_�[�Ƀ��[�_�[�V�b�v������������A���ʂƂ��ă��[�_�[�����[�_�[�V�b�v��������ԂɂȂ�B
�����ł���A���[�_�[�V�b�v�̓}�[�P�e�B���O���B�����Ƀ����o�[�������ł���r�W����������A�����Ƀ����o�[�����͂�������ڕW������A�����Ƀ����o�[�����҂���T�|�[�g������B���������o�[�Ɏv�킹�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����B
������������āA�r�W���������낤�A�ڕW�����낤�A�x���I�ɐڂ��悤�A�Ǝ����̓����o���悤�Ɍʂɍl���Ă����A�����̒��ɑS�̂͂Ȃ���ԂŐi�ނ��ƂɂȂ�B�����őS�̂������Ă��Ȃ��̂�����A����ɂ��S�̂������Ȃ��B�S�̂��`���Ȃ���A�����������̂��Ӗ����`���Ȃ��B�������ȁh�킴�Ƃ炵���h�����ɂȂ�B
�`�[���̑S�̂������Ă���Ƃ́A�`�[���̏��������͂�����Ƌ�̓I�ɃC���[�W���ł��āA���Ƃ���D�ɗ����Ă����Ԃ��낤�B�D�ɗ����Ă���A�r�W������ڕW����o�[�Ƃ̐ڂ����Ȃǂ͂������玩�R�ɏo�Ă���B�f�t�s�r�i�����D�j���o�Ă���B���[�_�[�V�b�v�͕��@�Ŕ�������̂łȂ��A������K�b�c�Ŕ���������̂��B
����̓}�l�W���[�ƃR�~���j�P�[�V�����ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N8��4���n
�@�@�@�@�@
�w�V�ēl���Ɠ��{�I�ȑg�D�iW�t����j�x�@�ivol.19�j
�u��������X�^�[�g�����V�̐��̑g�D�����A���܂��@�\���Ȃ������悤���ȁB�v�u�����ł��ˁA�����͑�_�ɑg�D�̐���ύX���܂��傤�B�v�u�g�D�}�͍l���Ă���B�v�u���Ƃ͒N�ɔC���邩�ł��ˁB�v�u���ꂼ��N���K�C���A�N�̈ӌ������Ă���B�v�u�V�݂̃}�[�P�e�B���O����́A�}�l�W���[���`����A���[�_�[���a����c�v
�g�D��ς��悤�Ƃ���Ƃ��A���喼��g�ݍ��킹���g�D�}������A���ꂼ��̕���̊K�w���ƂɍœK�ȃ����o�[��z�u����B���̃v���Z�X�ŏd�v�Ș_�_�́A�h�N���ǂ��ɔz�u���邩�h�ɂȂ�B�g�D�̋@�\�͕��喼�܂łŎv�l���~�܂��Ă��āA�e����̋@�\�́h�Ȃ�ƂȂ��h���L����Ă���B���̋��L�̊����́h������h�̌ċz�ɋ߂��B
�Ⴆ�A�h�c�ƕ���͔���Ɨ��v���グ�邱�Ƃ��d�����h�Ƃ������ʂ̔F��������A����ȏ��̓I�ȋc�_�����邱�Ƃ��Ȃ��A�����ɖ������o���l�����Ȃ��B�N���^���������ƂȂ��A�h�N���ǂ��ɔz�u���邩�h�̋c�_�����M����B���l�I�Ȏ��_�őg�D�������Ă����̂��A���{�̑g�D�̓����Ƃ�����B
���x�o�ϐ����̎���ɁA���{�̑g�D�łقڊ����ɋ@�\�����̂��A�I�g�ٗp�ƔN������̂����݂��B�I�g�ٗp�́A�S�Ă̎Ј����V�������N�܂ōݐЂ���̂��O��̂��߁A���̐l�𒆒����I�ɂǂ����������Ƃ������l�I�Ȏ��_�ɂȂ�B�N������́A�N�������l�ςƂ��āA�N���ォ�����Ƃ������S���ƂȂ邽�߁A��͂葮�l�I�Ȏ��_�ɂȂ�B
���n�o�ςƏ��q����ɂ��A�I�g�ٗp�ƔN�������藧�����͂Ȃ��Ȃ�A���ʎ�`�����̋~����ƂȂ�͂��������B���ʎ�`�͌��ʂŋ��^�����߂邵���݂��A�Ɛ��Ԃł͔F������Ă���B���������̖{���́A�g�D�l�I�Ȏ��_�ő�����̂łȂ��A�g�D���d���̐��ʂƂ������_�ő�����Ƃ����A����Αg�D�̉^�c���j�i��`�j���B
�{���̐��ʎ�`�ł́A�h���̑g�D�ɂƂ��Đ��ʂƂ͉����h���l���邱�Ƃ��A�ł��d�v�ȃv���Z�X�ɂȂ�B�_�_���l����g�D���̂��̂Ɉڂ��Ă���B���ꂪ�Ӗ����邱�Ƃ́A�h�Ȋw���邱�Ƃ��ł���h�Ƃ������Ƃ��B�l�̐��_�͖ڂɌ����Ȃ����A����ł��Ȃ�����Ȋw�̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��B�i�䂦�ɁA�Ȋw�͔]�_�Ƃ݂Ȃ��Ĕ]�g�𑪒肷��B�j
�l�̐��_�͑��l���`�����葪�肵���肷�邱�Ƃ͐�ɂł��Ȃ��̂ŁA���S�ɂЂƂ�̐l�̒��ɕ��Ă���B����őg�D�́A������ڂɌ����Ȃ����̂ł͂��邪�A�����̐l���ЂƂ̑ΏۂƂ��Ē��ۉ����A���L���邱�Ƃ��ł���B�����͂����Ȃ̂������܂������Ȃ��̂́A���{�l�������Ă��鑮�l�I�ɑg�D�𑨂���X���Ȃ̂�������Ȃ��B
�T�b�J�[���{��\�̃u���W�����[���h�J�b�v�ꎟ�\�I�s�ނ����܂��Ă����ɕ��ꂽ�̂��A�V�ē̐l���ł������B�X�|�[�c�V����ʂɂ́h�����W���p���a���I���h�B����܂ŔM���I�ɕ���Ă����h�U�b�N�E�W���p���h�̃U�b�N�ḗA���͂�ߋ��̐l�I�ȋ��D��Y�킹�āA�ЂƂ�₵���A���̓r�ɂ��Ă��܂����B
���[���h�J�b�v�J�ÑO���烁�f�B�A�̊S�i�����Ԃ̊S�j�́A�ē̐l������сA�e�I��̐l������тɌ������Ă����B�N����\�I��ɑI���̂��A�N���\�I��ɂ���ׂ����B���J�Ì�́A�N���o�ꂷ��̂��A�N���o�ꂳ����ׂ����B�`�[���̑g�D�Ƃ��Ă̐헪���p�̖������A���l�I�Ȗ�肪�_�_�ɂȂ��Ă����B
���{�R�̑g�D�_�I�����_�w���s�̖{���x�i�U���̋����j�ɂ͂����q�ׂ��Ă��܂��B
�����悻���{�R�ɂ́A���s�̒~�ρE�`�d��g�D�I�ɍs�����[�_�[�V�b�v���V�X�e�������@���Ă����Ƃ����ׂ��ł���B�i�����j���s������@�A��p�A�헪�͂��A���̉��P���T�����A�����g�D�̑��̕����ւ��`�d���Ă����Ƃ������Ƃ͋����قǎ��s����Ȃ������B����͕������Ȋw�I�E�q�ϓI�ɂ݂�Ƃ�����{�p��������I�Ɍ����Ă������Ƃ��Ӗ�����B��
�u���W�����[���h�J�b�v�œ��{��\���ꎟ���[�O�Ŕs�ނ��A���̌����Ɖۑ�͂���悤�ȃ��f�B�A�̋c�_�͂Ȃ��A�V�ēl������Ԃ̃g�s�b�N�ƂȂ����B���f�B�A����������邩�́A���Ԃ��������߂Ă��邩�Ƃقړ��ӂ��B���̌��ۂ́A���{�l�̑g�D�ɑ���ӎ����g�D���̂��̂łȂ��A�l�Ɍ������Ă��邱�Ƃ̏ے��ł͂Ȃ��������B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ń}�l�W���[�̎����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���u�������������v�����u�N�����������v�ɂ��傫�ȊS�����l�����A�}�l�W���[�̒n�ʂɂ���ׂ��ł͂Ȃ��B�d���ɋ��߂���v�������l�����d������̂́A���ł���A����������������B��
���{�l�͂��Ƃ��Ƒ��l�I�ɑg�D�𑨂���X���������Ă���悤���B�厖�Ȃ��Ƃ́A���̌X�������P����Ƃ��������A���̂��Ƃ����o���������ŁA�g�D���q�ϓI�ȑΏۂƂ��đ����Ă������Ƃ��낤�B���������_��ς��邱�ƂŁA������p�������Ă���B�u�N�����������v�ł͂Ȃ��A�u�������������v�̎��_�őg�D�����ߒ������Ƃ�����B
����̓}�l�W���[�ƃ��[�_�[�V�b�v�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N7��14���n
�@�@�@�@�@
�w�ӎ��ƃS�[���O�̉��p�X�iW�t����j�x�@�ivol.18�j
�u�T�b�J�[���{��\�̃u���W�����[���h�J�b�v���I������B�ΐ푊��ɔ�ׂē��{�̑I��̓S�[���̈ӎ����s�����Ă����ȁB�v�u�����ł��ˁB�S�[���O�̉��p�X�ɂ̓C���C�����܂����ˁB�v�u�Ƃ���őO���̔���ڕW�͒B���ł������ȁH�v�u���݂܂���B�������ł��B�v�u�U�߂�ӎ����s�����Ă��B�v�u�͂��A�ӎ����Ċ撣��܂��B�v
�m�[���b�g�����_�[�V���͒����w���[�U�[�C�����[�W�����i�ӎ��Ƃ������z�j�x�Ō����҃��x�b�g�̎�������ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
���ӎ���������ɂ͂قڂO�D�T�b�̔]������K�v�Ƃ���B����́A���o�o���ł���ӎv����ł���ς��Ȃ��B�O�҂̏ꍇ�A��ϓI���Ԃ̌J��グ���N���邽�߁A���o�h���̔������_�Ŏ��o���������悤�Ɋ�������B��҂̏ꍇ�A�ӎv���肪�v���Z�X�̑��i�K�Ƃ��Ċ������A���̑O�ɋN���Ă����O�D�T�b�̔]�����͈ӎ�����Ȃ��B��
�l�Ԃ��h�ӎ����āh�s������Ƃ��A���ۂ͂��̂O�D�T�b�O�ɖ��ӎ��������o���A�ӎ��͖��ӎ��ɂO�D�T�b�x��Ă����F������B�������A�ӎ��͎��Ԓ������s���āA���ӎ��������o�������ԂɁh�ӎ��������h�̂��ƍ��o������B�����ňӎ����Č��߂��Ǝv���Ă����s���́A�O�D�T�b�O�ɖ��ӎ������߂��s������ǂ��ňӎ����F�����Ă���B
�g�D�Ŗ�肪���������Ƃ��A�Ĕ��h�~�̂����݂�V���ȃ��[���Ȃǂ̉����������̂��ʏ킾�B�������A��������s����̂́h�ӎ�����h�l�Ԃł���Ј����B�Ō�́u���������J��Ԃ��Ȃ��悤�Ɂh�ӎ����āh�s�����悤�B�v�Ɛ錾���ďI���̂͊Ԉ���Ă��Ȃ��B�������A�h�ӎ����čs������h�͂قƂ�ǎ��s���ꂸ�ɏI���B
���ӎ����ӎ�����s����Ȃ�A�ӎ����ǂ����邩�ł͂Ȃ��A���ӎ����ǂ����邩���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ӎ��͈ӎ��ł��Ȃ����疳�ӎ��Ȃ̂�����A�ӎ��ł͉����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�ł͂ǂ����邩�B�s����ς��邽�߂ɂ́A���]�Ԃɏ���܂ł̃v���Z�X�̂悤�ɁA���ӎ��œ�����܂ŁA�������g�̂��g���ČJ��Ԃ����K����B
�w���[�U�[�C�����[�W�����x�ł͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�����x�b�g�̎������ʂ́A�������Ɏ��R�ӎv�͂Ȃ��A�ƌ����Ă���̂��낤���B�ӎ��ȊO�ɁA���R�ӎv���s�g�ł�����̂͂��肦�Ȃ��̂�����B���L���ĕ�����邱�Ƃ����߂��Ǝv�����Ƃ��́A���łɔ]���������Ă���̂��Ƃ�����A�l�ԂɎ��R�ӎv������Ƃ͌����������B��
�������ɁA�l�Ԃ͖��ӎ��ɏ]���čs�����Ă��āA�ӎ��͂������ǂ��ŔF�����Ă���̂�������Ȃ��B���N�ċx�ݑO�ɏh��̌v��𗧂āA��O�Ȃ��W�����{��J�T�ȋC���Ō}����B�ӎ��͑����h����ς܂��悤�ƈӋC���ނ��A�g�̂����Ă��Ȃ��B�_�C�G�b�g�������ӎ�������A�C��������H�ׂĂ���B���ӎ��̏����A�ӎ��̔s�k�B
�w���[�U�[�C�����[�W�����x�ł͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
���ӎ���������͔̂]���������ォ������Ȃ����A����͎肪�����O�ł�����B���ӂ��ӎ����Ă��炻�ꂪ���s�Ɉڂ����܂łɂ͂O�D�Q�b�̗]�T������B���Ƃ�����A�ӎ��͂ǂ��ɂ����Ď��s�𒆎~�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�i�����j�ӎ��͍s�ׂ��N�������Ƃ͂ł��Ȃ����A���s���Ă͂����Ȃ��Ƃ������f�͂ł���̂��B��
�ӎ������ӎ��̓������ӎ�����܂łO�D�T�b�����邪�A�܂��������������B�ӎ����Ă���s���Ɉڂ�܂łO�D�Q�b������B�ӎ��͂�������s�Ɉڂ����ǂ����̌��f�����邱�Ƃ��ł���B�ӎ��͖��ӎ��ɑ��āA��Ă͂ł��Ȃ������ی������͎����Ă���B
���ӎ��ɔC������܂���������������Ȃ��s�����A�ӎ������f���Ĕے肷�邱�Ƃ�����B�u���W�����[���h�J�b�v���{��\�́A���킩��h��ɕ������Ȃ��킢�h�ƃ��f�B�A�ɒǂ����܂�A�N�����S�[�����h�ӎ����āh�����͂����B���i�ʂ�Ɂh���ӎ��Ɂh�����Ă���S�[���O�Ŏ��R�ƃV���[�g�ł������A�����ӎ����u�ԓI�ɖ��ӎ��̃V���[�g��ے肵�āA���p�X��I�����Ă��܂����̂�������Ȃ��B
�ӎ������ی����������Ȃ��Ȃ�A�d���ɂ�����������̏�ʂł��u�ӎ����Ċ撣�낤�v�u�����C�����ōs�����v�Ƃ������_�����ł́A�t���I�Ɏ��s�������������B���̈ӎ�����ɁA�g�̖̂��ӎ����ǂ��P�����邩�i�ǂ�������ӎ����Ȃ��Ă��]�܂����s������ɂł���悤�ɂȂ邩�j���e�[�}�ɋc�_����K�v�����肻�����B
����̓}�l�W���[�ƃ��[�_�[�V�b�v�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N7��1���n
�w�}�l�W���[�͉����d���ɂ���l���i��j�x�@�ivol.17�j
�u�}�l�W���[�̎d���̓`�[���̎����n��グ�邱�Ƃ��B�v�u�������A���ΐ����_�Ȃ̂��B�v�u���ԂƋ�Ԃ���̂ɂȂ��Ă���H�v�u���Ԏ��̑������ł��A��Ԃ̑������ł�����Ȃ��̂��B�v�u�A�C���V���^�C���B�B�v�u���������ۂ́A�ǂ��炩���ӂȕ��Ń`�[�����}�l�W�����g���Ă���}�l�W���[�������̂��B�v�u�j���[�g���B�B�v
���������݂��Ȃ������Ɏ��Ԏ������邱�Ƃ́A���̍��ɈӖ���^���邱�Ƃ��B�l�Ԃ͈Ӗ��������Ă��܂����������B�Ӗ��������Ȃ��Ƃ���ɁA��M��`�x�[�V�����͐��܂�Ȃ��B�Ӗ��͎��Ԃ̗���̒��ɂ���B�t�Ɍ����ƁA�l�͎��Ԃ̗���������邱�Ƃ��ł��邩��A�Ӗ��������邱�Ƃ��ł���B
�d���ɈӖ�����������̂́A�l�Ԃ�����������Ȃ��B���̐������́i�����Ă݂Ȃ���킩��Ȃ����A�l�Ԃ����t�ňӖ���������Ƃ���j���Ԃ̗���������邱�ƂȂ��A�Ӗ��������邱�ƂȂ��A���̏u�Ԃ����������Ă���悤�ɂ݂���B�l�Ԃ͂Ƃ��ǂ���c�ɖ߂��āA�d���ɈӖ��������Ȃ��Ȃ�B�}�l�W���[�͎d���ɈӖ���h�点��B
�܂��͎��Ԏ������邽�߂ɁA�������Z�b�g����B��������Ɩ����ƌ��݂̊ԂɈ�{�̐����ł���B�������猻�݂ւ̎��Ԏ����ł���A���̉�������ɉߋ��̈Ӗ��������オ���Ă���B���ɋP�������̐�����A�ЂƂ̐��Ő����������オ��B�Ӗ��͏��߂��炠��̂ł͂Ȃ��B�}�l�W���[�͖����̉\������A�Ӗ����ЂƂɌŒ肳����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ń}�l�W���[�̎d���ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���}�l�W���[�̎d���͂T�̊�{�v�f����Ȃ�B�����̕����������ƁA���܂��܂Ȍo�c�������ЂƂɂ܂Ƃ܂�A�����̂̂悤�ɐ������Ă����̂��B�@�ڕW�ݒ�A�A�g�D�Â���A�B���@�Â��ƃR�~���j�P�[�V�����A�C�Ɛѕ]���A�D�l�ވ琬�ł���B��
�}�l�W���[�����Ԏ�������d���Ƃ��āA�������Z�b�g����̂��@�ڕW�ݒ�A�ߋ��̈Ӗ��Â�������̂��C�Ɛѕ]�����B���Ԏ��͉����ł����A�r�{�ƕ���Z�b�g���B���̒��ŐS���������l�Ԃ�����������B�����̋�Ԃ͔z���Ɩ��҂̉��Z�ł�����B�����Ė��҂̐��ݗ͂��ő�Ɉ����o�����o���A�ō��̋�Ԃ�n��グ��B
�}�l�W���[����Ԃ�����d���Ƃ��āA�r�{�ɍ����z�������߂�̂��A�g�D�Â���A���ꂼ��̖��҂ւ̉��o���B���@�Â��ƃR�~���j�P�[�V�������B�}�l�W���[�͎��Ԏ��Ƌ�Ԃ������Ƃ�ʂ��āA�`�[���̕����n��グ��B�`�[���ɕ��ꂪ�ł��邩��A���̕���ɎQ���������Ɠ��@�Â����A����ɂ��Ęb�����������Ȃ�B
������i�̊�悲�ƂɃI�[�f�B�V�������s���ꍇ�́A���̓s�x��i�ɍł��K�������҂��W����B��������Ƃ̏ꍇ�́A���ɂ���Ј��̒�����z����I�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Œ胁���o�[�Ō������s�����c�̃C���[�W���B�����ŇD�l�ވ琬���K�v�ɂȂ�B�����郁���o�[���ǂꂾ�������ł��邩�B�����Ɍ��c�̐������������Ă���B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�łT�̊�{�v�f�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���ڕW�ݒ�A�g�D�Â���A���@�Â��ƃR�~���j�P�[�V�����A�Ɛѕ]���A�l�ވ琬�́A�����܂ł��`�̂����ł̕��ނł���B�����ɍ��𐁂����݁A��̓I�ňӖ�������̂ɂ�����̂́A�}�l�W���[�̌o���iexperience�j�������B��
"experience"�͎���������A"ex"�{"peril"�ɕ����邱�Ƃ��ł���B�댯�i
peril�j����iex�j�B�o���Ƃ́A�����Ċ댯�ɒ���Œ͂ݎ����̂ł���B�}�l�W���[�̎d���́A�͂T�̊�{�v�f���`���I�ɂ��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B�������U�߂̎p���ŐϋɓI�Ƀ��X�N�����A����̎d���ɍ��ƈӖ��𒍓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����̓}�l�W���[�ƃ��[�_�[�V�b�v�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N6��16���n
�w�}�l�W���[�͉����d���ɂ���l���i�O�j�x�@�ivol.16�j
�u��������O��̃}�l�W���[�ɂȂ�܂����B�v�u���߂łƂ��A���Њ撣���Ă��ꂽ�܂��B�v�u�ł��}�l�W���[�̎d�������܂��C���[�W�ł��Ȃ���ł��B�v�u����͐������Y�݂���B�v�u�͂��B�v�u�}�l�W���[�͂��ׂ����Ƃ��������āA�Ȃ��Ȃ��ꌾ�ŗv��ł��Ȃ��̂��B�v�u�ӂށB�v�u���������Ȃ�̃C���[�W�������Ƃ͂������d�v���B�v
�u�����Ȃ�ɃC���[�W���Ă�����ł��ˁB�v�u�����̂��ׂ����Ƃ�����������ł���B�v�u��͂�B�v�u�܂��̓h���b�J�[�̃}�l�W�����g��ǂ�ŁA�����Ȃ�̍l���������Ăق����B�v�u�킩��܂����B�v�u�S���o���悤�Ƃ���ƍ��܂��邩��A�����Ȃ�ɏœ_���i���ĉ��������邱�ƁB���̌�́A���Ȃ���C�����Ă��������B�v
�u�}�l�W���[�̎d���͉����H�v�Ɖ��߂ĕ������ƁA�ꌾ�œ�����̂͂Ȃ��Ȃ�����B����̂悤�ɕ��G���������ł́A�}�l�W���[�̂��ׂ����Ƃ����G�ɂȂ��Ă���B�ɂ�������炸�A�g�������d���h�̕����͍����������Ă���B�u���d���́H�v�u�c�ƕ����ł��B�v�l�ގs��ł́A���Ɨ��������Ă���Ƀ}�l�W���[���s�����Ă���B
���{�̍��x�������x�����N������̒u���y�Y���B�N������̕����ł́A�d���̓��e��������̊i�t���ɊS���������B�h�}�l�W���[�͉����d���ɂ���l���h�����A�h�}�l�W���[�ɂȂ邩�ǂ����h���d�v�Ȏ�肾�B����̎����͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��B�j�[�`�F�͐l�Ԃ̖{�����h���͂ւ̈ӎv�h���Ɗ��j�������A����̊������͋��S�n���悢���̂��B
�g�D������̎�������������߂ɂ́A����łȂ������ƐӔC�̎��_�Ŏd���𑨂������B�d���̈Ⴂ�͏���̈Ⴂ�ł͂Ȃ��A�����ƐӔC�̑傫���̈Ⴂ�ł����āA�����ɏ㉺�͂Ȃ��Ƃ���������z���Ă����B�}�l�W���[�̎d�����l���邾���ł��A�����̎��Ԃ��K�v�ɂȂ�B�������A�ς��悤�ƈӐ}���Ȃ���A���t���������͕ς����Ȃ��B
�}�l�W���[�͉����d���ɂ���l���B�܂��͑傫�Ȏ��_���瑨���āA�S�̑�����Ղ���B�O�[�O���}�b�v���g�債�Ă����悤�ȃC���[�W�ŁA�傫�Ȏd���̃C���[�W������ۓI�Ȏd�����e�ւȂ��Ă����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ń}�l�W���[�̎d���ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���}�l�W���[�̋�̓I�Ȏd���͂ӂ�����B�ЂƂ́A��S�̂Ƃ��Ă܂Ƃ߂����A�̑��a�ȏ�̐��Y���������o���d���ł���B����Ӗ�����́A�����y�c�̎w���҂̖����Ɏ��Ă���B�w���҂̓w�́A�r�W�����A���[�_�[�V�b�v���e�Z�N�V�����ɑ�����^���A�S�̂Ƃ��Ē��a�̂Ƃꂽ���t����������B�������A�w���҂���ȉƂ��������y���ɗ���A��������߂��Ă���ɂ����Ȃ��̂ɑ��āA�}�l�W���[�͍�ȉƂƎw���ҁA�����̖��������˂Ă���̂��B��
�}�l�W���[�͍�ȉƂƎw���ҁA�����̖��������˂Ă���B�y����^�����Ďw��������̂́A�s���~�b�h�g�D�Ńg�b�v�̎w�����ɓ`���钆�ԊǗ��E�̃C���[�W���B�}�l�W���[�͍�ȉƂł�����̂ŁA�����̃`�[�����ǂ�Ȍ����Ȃ�t�ł邩�A�e�����o�[�͂ǂ�ȃp�[�g�����t���邩���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�e�����o�[�ɂ͂��ꂼ��̋�̓I�Ȗ����i�p�[�g���j�������Ȃ���A�`�[���S�̂Ƃ��Đ��ݏo���ׂ���̓I�Ȑ��ʁi�ȑS�́j�̃C���[�W�����L������B�}�l�W���[������̃`�[�����v���f���[�X���銴�o���B�����o�[�X�̃L�����N�^�[�����点�āA�`�[���S�̂Ƃ��Ĕ����I�[�P�X�g���Ɉ�Ă�����B�}�l�W���[�̖����̓v���f���[�T�[�ɋ߂��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ő����Ă��������Ă��܂��B
���}�l�W���[�̎d���̂ӂ��ڂ́A���f����������A�s�����N�������肷��ۂɂ͕K���A���ʂƏ����̗v�������܂����a������A�Ƃ������̂ł���B��
�`�[����������邽�߂ɉ������邩�l����̂Ɠ����ɁA����������Ă��邽�߂ɉ������ׂ������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�A�C�h���O���[�v�Ȃ�l�C���ō����ɒB���������̂Ƃ��ɁA�����Ɍ����Ă����ă����o�[�����ւ���B�������Ă���Ƃ��ɁA������ς��锻�f�͉����ɂ����B�������A���̐������i���ɑ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��B
�}�l�W���[���I�[�P�X�g������ō��̉��t�i�`�[������ō��̐��ʁj�������o�����Ƃ��A�}�l�W���[�͂����ɍō��̋�Ԃ�n��グ���Ƃ�����B�܂��A���݂Ə��������܂����a������ꂽ�Ƃ��A�}�l�W���[�͂����Ƀ`�[���̎��Ԏ���n��グ���Ƃ�����B�}�l�W���[�̎d����傫��������A����͂���`�[���̎����n��グ�邱�Ƃ��B
����͈��������}�l�W���[�̎d���ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N6��2���n
�w�ڕW�Ǘ��ƃZ���t�R���g���[���i��j�x�@�ivol.15�j
�u�X�|�[�c�͉�������Ă܂��H�v�u�}���\������Ă܂��B�v�u�����A�}���\�����ĂP�l�łЂ����瑖�邾���̂���H�v�u�����A�܂��B��������������ł��ˁB�v�u���������g�̓������Ȃ�X�|�[�c�̂ق����ʔ����ł���B�v�u�܂��B�v�u���T���e�j�X����Ă��ňꏏ�ɂ��܂��H�}���\�����X�|�[�c�̂ق����y�����ł���B�v
�l���������l����Ƃ��A�O�Ȃ���l���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�킽�������́A�m�炸�m�炸�̂����ɑO���u���Ęb���Ă���B�h�}���\���̓X�|�[�c���h�Ƃ����O��̂`����ƁA�h�}���\���̓X�|�[�c�ł͂Ȃ��h�Ƃ����O��̂a����̊Ԃł́A�O��̈Ⴂ���ӎ�����Ȃ��������b�����ݍ���Ȃ��B
�O��͖��ӎ��ɒu����邽�߁A�������O���u���Ęb���Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ��B�R�~���j�P�[�V�����̐����������Ă���v���̂ЂƂ��B�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�u�Ȃ�ł킩��Ȃ����ȁB�Ȃ�ł킩���Ă���Ȃ����ȁB�v�ƈ���I�Ɏv���A�Ō�ɂ͂������Ȃ�������߂�B������h�o�J�̕ǁh�������͂�����B
�u�ڕW�ɂ���ăZ���t�R���g���[���ł���}�l�W�����g�ł���̂��B�悵�A����������H���悤�B�v�u���[�A���܂ł͖ڕW�Ǘ��ŖڕW�Ǝ��т̍����������Njy���܂������A��������͂�߂܂��B�݂�Ȏ����Ŏ����̍s�����R���g���[�����āA�ڕW�B�����Ă��������B���ꂪ�{���̖ڕW�Ǘ��ł��B�v�u���̋S�̒Njy���Ȃ��Ȃ�̂��B���b�z�[�B�v
�u���T�̉c�Ɖ�c�ɑウ�āA�����̕���͂��߂܂��B��c�������ĉc�Ƃ̎��Ԃ����������A�������ʂ����҂��Ă��B�v�u���`�A�����̖ڕW�B���x�͂T�O���ł��B�v�u���`�A�����̖ڕW�B���x�͂S�O���ł��B�v�u�o�J�����[�A�B���x�������Ă邶��Ȃ����B�����̍s�����R���g���[�������̂��H�v�u�͂��A�����ŗD�揇�ʂ��ē����Ă܂��B�v
���ۂɂ͖��T�̍s���v�����̌������t�H���[���Ȃ��Ȃ������ƂŁA�قƂ�ǂ̉c�ƃ}���͍s���̎��Ɨʂ������Ă����B�s���₷���ڋq�����K�₵�A�{���K�₷�ׂ��������ڋq�ւ͍s���Ȃ��Ȃ����B�Ј��ɂ̓Z���t�R���g���[���Ƃ��������������������Ă����B�u�l�͎����̕����������̂��������Ȃ��B�v�Q�O�O�O�N�O�ɃJ�G�T���͂Ԃ₢���B
�����ɂ́h�ڕW�𗧂Ă�ΐl�͂����Ɍ����čs��������̂��h�Ƃ����O�u����Ă���B�������x������Ƃ��ɂ́A�l�͋@�B�̂悤�ɐ��x�ɂ��Ă���ƍl���������B���x�𗘗p����̂͂ЂƂ�ЂƂ�Ⴄ�S���������l�Ԃ��Ƃ������Ƃ�Y�ꂪ���ɂȂ�B�R���Z�v�g�Ƃ��Ă̖ڕW�Ǘ��̎����ɂ́A�l�ɏœ_�Ă��O�K�v�ɂȂ�B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŖڕW�Ǘ��ɂ��Ă��������Ă��܂��B
��management by objectives and self-control�i�ڕW�Ǘ��ƃZ���t�R���g���[���j�́A�u�l�X�͐ӔC�����������A�v���������A���ʂ����������A�Ɩ]��ł���v�Ƃ�������̂����ɐ��藧���Ă���B��
�ڕW�Ǘ��𐧓x�Ƃ��ē������Ă����܂��@�\���Ȃ��̂́A���̑O����������Ă��邩�炾�B���������@�_�łȂ��A�R���Z�v�g�ł���䂦�B�ڕW�Ǘ��ƃZ���t�R���g���[�����@�\�����邽�߂ɂ́A�Ј��̎d���ւ̌����������@����K�v������B�����A�ӔC��v���A���ʂƂ������t���S�ɋ����Ȃ��Ȃ�A�{���̖ڕW�Ǘ��͋@�\���Ȃ����낤�B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŖڕW�Ǘ��ɂ��Ă���ɂ��������Ă��܂��B
�����́h�N�w�h�Ƃ������t���y�X�����͎g��Ȃ��B�ނ���A���������g�킸�ɂ��܂��������炢�ł���B�h�N�w�h�͂��܂�ɏd�����t�����炾�B�ɂ�������炸�A�ڕW�Ǘ��ƃZ���t�R���g���[���ɂ��ẮA�u�}�l�W�����g�̓N�w�v�ƌĂԂ̂��ӂ��킵���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B��
�ڕW�Ǘ��́A�d����l���Ǘ������i�Ƃ��Ďg������̂ł͂Ȃ��B�h�Ј��͐ӔC�����������A�v���������A���ʂ����������A�Ɩ]��ł���h�Ƃ����N�w�i�v�z�j��O��Ƃ��āA�����������Ƃ����ӎv������i�����܂������Ă��Ȃ��j�Ј����A���ʂ��o���₷�����������i�Ƃ��Ďg����ׂ����̂��B
����̓}�l�W���[�̎d���ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N5��19���n
�w�ڕW�Ǘ��ƃZ���t�R���g���[���i�O�j�x�@�ivol.14�j
�u�����݂�ȕ����Ă���B�ڕW�Ǘ��̈Ӗ��́A�h�ڕW�̊Ǘ��h����Ȃ��āA�h�ڕW�ɂ��Ǘ��h�Ȃ��āB�v�u���A����Ȃɂ��ɗL���Șb������B�ڕW�Ǘ��́A�h���b�J�[�������hmanagement
by objectives�h������̂ł���B�v�u����A�m���Ă��́B�v
�u�Ƃ���Ŏ����Ō����Ă����ĉ��Ȃ��ǁA�h�ڕW�̊Ǘ��h�Ɓh�ڕW�ɂ��Ǘ��h���Ăǂ��Ⴄ���H�v�u�h�ڕW���Ǘ�����h���A�h�ڕW�ɂ���ĊǗ�����h���̈Ⴂ�ł��傤�B�v�u������Ɖ������Ă邩�悭�킩��Ȃ��ȁB�����Əڂ����������Ă�B�v�u�͂��B�v
�u�h�ڕW���Ǘ�����h�́A�Ǘ�����Ώۂ��ڕW�ł���ˁB�h�ڕW�ɂ���ĊǗ�����h�́A�Ǘ�����Ώۂ��ڕW�Ƃ͕ʂɂ���Ƃ������Ƃł���B�d���Ƃ��l�Ƃ��B�v�u�Ȃ�قǁA�ڕW�Ŏd����l���Ǘ�����̂��B�ڕW�Ǝ��т��ׂĊǗ�����B�v�u�����ł��B�v
"management by objectives"���h�ڕW�Ǘ��h�Ƃ���A���R�Ɓh�Ǘ��h�Ƃ������t�������яオ��B�L�����Łu�Ǘ��v�������Ă݂�ƁA�u�@�NJ����������邱�ƁB�ǂ���Ԃ�ۂ��ƁB�Ƃ肵���邱�ƁB�v�Ƃ���B�n���I�Ƃ������́A�Ώ��I�ȃC���[�W���B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ł��������Ă����B�i�R����Vol.1�Čf�j
���u�}�l�W�����g�v�́A���Ƃ̂ق�������t�ł���B���������A�����J�ɓƓ��̌��t�ł��邽�߁A���̌���ɂ͂��悻�悤���Ȃ��B�C�M���X�p��ɂ���Ȃ��B��
�����̃^�C�g���wManagemet�x�͓��{��łł����̂܂܁w�}�l�W�����g�x�����A�������́hmanagement by objectives�h�̖�́h�ڕW�Ǘ��h���B��C�͂悢���A���t�̗͂͋����B�Ȃ��ݐ[���h�Ǘ��h�Ƃ������t�Ɉ���������B�����āA�v�����݂����L�����B
�h�ڕW�Ǘ��h���h�l�a�n�h�Ɨ������Ƃ����邪�A�h���b�J�[�͌����Łh�l�a�n�h�Ƃ���������g���Ă��Ȃ��B�hmanagement by objectives�h�ɂ͑����������āA�hand
self-control�h�����ă����Z�b�g�̊T�O���B�ʁX�Ɏg���Ă��镔�������邪�A�قځhmanagemant by objectives
and self-control�h�Ƒ����Ďg���Ă���B
�h�ڕW�ɂ���ĊǗ�����h�Ƃ������@�_�ł͂Ȃ��A�h�ڕW�ɂ���Ď��ȃR���g���[�����ł���A�}�l�W�����g���\�ɂȂ�h�Ƃ����R���Z�v�g�Ȃ̂��B��肽���̂͊Ǘ��ł͂Ȃ��}�l�W�����g������A�hmanagement�h�Ɓhby
objectives and self-control�h�ƕ��߂���ق�����|�ɍ����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�łl�a�n���r�b�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���hmanagement by objectives�h�́A���Ƃ��}�l�W�����g�`�[���̕�������w�͂̑Ώۂ�ɓ����Ȃ��Ƃ��Ă��A�hmanagement
by self-control�h���\�ɂ��邽�߂ɂ͕K�v�Ȃ��̂ł���B��
�u�����̉c�Ɖ�c�͂��߂܂��B��������A�ڕW�B���x�͂ǂ��H�v�u���`�A�����͌������ł��āA�B�����͂U�O���ł��B�ǂ�������悢�ł��傤���H�v�u���`�A����������ōl����̂��d���ł��傤��B�v�u���݂܂���A�Ƃɂ����K���Ŋ撣��܂��B�v
��i���������v�l��~��Ԃ��B�h�ڕW�Ǘ��h���Ă���Ǝv������ł��邩��A�v�l��~�ɋC�Â��Ă��Ȃ��B�Z���t�R���g���[���Ƃ́A�����ōl���s�����邱�Ƃ��B�ڕW�́A�}�l�W���[���������Z���t�R���g���[�����Đ��ʂ��o�����߂Ɏg���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�łl�a�n�i���r�b�j�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
�����S���̊�Ƃ��h�l�a�n�h���̗p���Ă��邪�A�^�́hself-control�h���������Ă����͂����ꈬ��ɂ����Ȃ��B�h�l�a�n���r�b�h�́A�P�Ȃ�X���[�K���A��@�A����ǂ��납���j�������������̂ł���B����A��{�����Ȃ̂��B�������������͗���Ȃ�
��Ȃ̂́A�ڕW�Ǘ��Ƃ����h��@�h���h�����h����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�h�ڕW�Ǘ��h�̎��H��ʂ��āA�O����̎w�����߂łȂ��A���Ȃ̓�������̃R���g���[���������o���B�����I�ȓ��@�Â��ɂ��A�m���J���҂Ƃ��Ď��琬�ʂݏo���g�D����������B
�h���ʎ�`�h�������悤�Ȍ�����₷���B���ʎ�`�Ƃ����h���x�h������̂ł͂Ȃ��B��`�Ƃ́A�قȂ�l�������ł���Ƃ��ɉ����d�v�ƍl���邩���B�Ⴆ�A����������ʂ��d�v�Ƃ���g�D���������ʎ�`���B���x�́A�g�D���������邽�߂̎�i���B
����͈��������ڕW�Ǘ��Ǝ��ȊǗ��ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N5��2���n
�w�g�D�K�w�ƒm���J���҂̗��ƃj���g���x�@�ivol.13�j
�u����ł͎В��A�V�N�x�X�^�[�g�̈��A�����肢���܂��B�v�u���`�A���N�x���瓖�Ђ̓t���b�g�g�D�ɕς��܂��B���݂͎В��ȉ��A���ƕ����A�����A�ے��A�W���A�S���ƂU�̊K�w�ł����A�В��A���ƕ����A�W���A�S���̂S�K�w�ɂ��܂��B���ꂩ��̓g�b�v�_�E���̎w�����ߌ^�g�D�łȂ��A����ŃX�s�[�f�B�ɓ��������g�D�̎���ł��B�v
�u����A�܂��͂��܂�����В��̎v�����B�v�u�m���ɁB�ł��ŋ߃g�b�v�_�E���̎w���ʂ蓮���Ă����ʏo�Ȃ����ȁB�v�u�t���b�g�g�D�̎�����Ă̂͊Ԉ���ĂȂ������B�v�u���܂ł̖��ʂ��g�c�̎��Ԃ��Ȃ��Ȃ邵�B�v�u����͎��R�ɓ����Ă悳�������B�v
�s��̎哱������Ƃ������Ă�������́A�������g�b�v�������Ă�������A������m���ɖ��[�܂Ŏw�����邱�Ƃ��g�D�̎g���ł������B�������A�ڋq��n�����邱�Ƃ��g�D�̎g���ɂȂ�������́A�����͌ڋq�ɋ߂��Ј��������Ă���B�s���~�b�h�g�D�ł��邱�ƂɕK�R���͂Ȃ��B���Ԃ��A�t���b�g�g�D���K�R�ɂȂ��Ă���B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�őg�D�K�w�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
����{���[���́A�}�l�W�����g�K�w���ł��邩���茸�炵�A�w�����ߌn�����ŒZ�ɂ��邱�Ƃł���B�悯���ȊK�w������ƁA���ݗ������W�����A���ʂ̕�����ڎw���Ȃ��Ȃ�B�K�w�������邽�тɖڕW���c�߂��A���ӂ��U���ɂȂ�B��
�w�����ߌn�����ŒZ�ɂ��邱�ƁB�悯���ȊK�w���Ȃ����ƁB�������藬���Ă��܂������ɂȂ邪�A�u�ŒZ�Ɂv�u�悯���ȁv�Ƃ������t�́A�����l����Ɓu�ǂ��`�v�Ǝv�킸�X���Ă��܂��B�`�e���͂������̂��B�����Ƃ̂��܂������ɂ͌`�e�����قƂ�ǂȂ����̂��B
�t���b�g�g�D�ɕς���ĂR�����オ�o�߂����B�V���Ȏ��ƕ����̓}�l�W���[�A�W���̓��[�_�[�ƌĂ�Ă���B�u�}�l�W���[�A��肪�������܂����B�ǂ�������悢�ł��傤���H�v�u�}�l�W���[�A��ςł��B���}�w�������������B�v�u�}�l�W���[�A���q���S�����Ղ�Ղ�ۂł��`�B�v�u�}�l�W���`�A�����ā`�B�v���[�_�[�͋��ԁB
�}�l�W���[�̌g�ѓd�b�͖��܂Ȃ��B���̓I�ɂ����_�I�ɂ��p���N���O���B�u�В��A���̃t���b�g�g�D���ςȂ�ł��B���ꂪ��炸�A�J�I�X�Ɋׂ��Ă܂��B�v�u�Ȃ��āH�t���b�g�g�D�ɂ�������A����őf�����Ή��ł���͂����낤�B�v�u�ł�����͒���w�������߂��ł��B�v�u�Ȃ�قǁA�����������Ƃ��B�v�u�͂��`�B�v
�u�g�D�}�������̂��悾�ƒm���āA�t���b�g�g�D�̓����͓��̒��ʼn��x���V�~�����[�V���������̂��B�����ł̌W���̖����͖��炩�������B����X�^�b�t�Ɏw������̂ł͂Ȃ��A������������錻��X�^�b�t���x�����邱�Ƃ��B�v�u�͂��B�v�u�������A���̒����������̂ł͂Ȃ��B���Ɛg�̂���̂ƂȂ��Ď��̂Ȃ̂��B�v�u�͂��`�B�v
�u�܂�A�t���b�g�g�D�Ɂh����h�̂ł͂Ȃ��A�t���b�g�g�D�Ɂh�Ȃ�h�Ƃ������Ƃ��B�v�u�Ƃ����܂��ƁH�v�u���ԂƂ��ẮA���ꃊ�[�_�[�ƃX�^�b�t�̃`�[���������I�ɓ����Ă��邱�Ƃ���ŁA��������Ǝw�����K�v�Ȃ��Ȃ邩��A���̌��ʂƂ��ăg�b�v�̎w��������ɓ`���钆�ԊǗ��E������Ȃ��Ȃ�B�v�u���`�B�v
�u���̒��͎����I�ɓ����ׂ����Ƃ킩���Ă��Ă��A�g�͎̂w���҂��̏K�����g�ɂ��Ă���B�������肪�N����悤�Ȏ��ԂɂȂ�ƁA�ǂ�������悢���킩�炸�w�������ł��܂��B�v�u�������B�t���b�g�g�D�͈�U���Ƃɖ߂��āA�܂��͎���������ł��郊�[�_�[�̈琬�Ɏ��g�ނ��Ƃɂ��悤�B�v
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŘJ���҂̕��ނɂ��Ă��������Ă��܂��B
���A�J�҂͂��ׂĒm���J���҂Ɠ��̘J���҂̂ǂ��炩�ɐF�����ł��邩�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B��
�m���J���҂̓z���C�g�J���[�A���̘J���҂̓u���[�J���[�Ƃ�����B���̘J���҂́A�K�i��ʐ��Y�̍H��ŌJ��Ԃ�������Ƃ�����J���҂̃C���[�W���B�������A���̂����g���Ȃ��Ƃ��Ă��A�����̓����g�킸�ɑ��l�̎w���ʂ�ɓ��������Ȃ�A�m���J���҂Ƃ͂����Ȃ����낤�B�����̓����g���Ďd��������̂��m���J���҂��낤�B
"�m���J����"�́A������"knowledge woker"�̖�ꂾ�B�I�b�N�X�t�H�[�h�p�p���T�ɂ��ƁA�hknowledge�h�i�m���j�Ƃ́A�hthe
information, understanding and skills that you gain through education or
experience�h�i�w�K�܂��͌o�����瓾�����A�����A�X�L���j�Ƃ����Ӗ����B
�m���邱�Ƃ́A�w�K������◝���邱�Ƃƍl���������B�l�b�g�Ō�������B����ɒm�邽�߂ɖ{��ǂށB�����Ő��j���邠��b�̏o�Ԃ��B�j�����̒m���Ŋ����ɗ��������Ƃ��Ă��A�����̐g�͉̂j�����Ƃ��ł��Ȃ��B�����̂͒m���̕Б������炾�B�hexperience�h�ɂ��hskill�h�āA�͂��߂Đ��j�́i�{���́j�m������B
����`�[���������I�ɓ������߂ɂ́A����`�[���̃��[�_�[�ƃX�^�b�t���m���J���҂ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������������邽�߂ɕK�v�ȏ��ŗ������A��������H�Ŏ����Ă������ŁA�����̐g�̂ɃX�L�����o�������Ă����B�����āA�������D�ɗ�����܂Őςݏd�ˁA���ōl���Ȃ��Ă��g�̂����R�Ɠ������x���܂Ŏ����Ă����B
����`�[���������܂Ő��������Ƃ��A�����I�ɑg�D�̓t���b�g�ɂȂ�͂����B�h�w�����ߌn�����ŒZ�ɂ���h�A�h�悯���ȊK�w���Ȃ����h�̓����́A���ʂƂ��Č��܂���̂��B�g�D�K�w�ƒm���J���҂̗��ƃj���g���́A�m���J���҂���A�g�D�K�w����Ƃ����������B
����͒m���J���҂ƖڕW�Ǘ��ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N4��15���n
�w�g�D�f�U�C���Ɓu���ƐÁv�̗Z���x�@�ivol.12�j
�u�݂�ȁA�o�b�`�����K���Ă����H�v�u�����[�����B�v�u���ꂶ��A�܂��͐V�Ȃ������Ă������B�v�u�P�A�Q�A�R�A�t�H�[�I�v����A�����������B�݂�ȖZ���������K���Ă��Ă�ȁB�������炪�V�ȍő�̌�����A�M�^�[�\�����B�����A�Y���Ă����B
�u��߁A��߁B�M�^�[����߂���B�v�u�����A�S�R�C�����Ȃ������B�v�u�C�����Ȃ������āA����̉����ĂȂ��������Ă��ƁH�v�u���A���������Ε����ĂȂ������B���͗��K�s���ŕ��ʂ����Ȃ���e���ĂĂˁB����Ŏ����̉��t�ɏW�����Ă��܂����B�v
�R�s�[�o���h�����߂ĐV�Ȃ����t����Ƃ��A�y���͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂��B�y����������̋Ȃ̑S�̑��Ɗe�y��ɋ��߂��鉉�t���@���킩��B�e�p�[�g���y���ǂ���ɉ��t����A���Ȃ��Č��ł���i�Ǝv���j�B�������A���ꂼ�ꂪ���ʂǂ��萳�m�ɉ��t�����Ƃ��Ă��A�{�Ƃ����t�����Ƃ��́h���̊����h�͂Ȃ��Ȃ��Č��ł��Ȃ��B
�{�Ƃ͍ŏ����畈�ʂǂ���ɉ��t���Ă���̂ł͂Ȃ��B��Ȏ҂͂P�l�ł��A�A�����W�͊e�y��̃����o�[���A�C�f�A���o�������A�Ȃ̕��͋C��n��グ�Ă����B���̉ߒ��ŁA�Ȃɔނ�̌����ɂ��ݏo�Ă���B���̉��t���̂��̂���ŁA���ʂ͌ォ��W���̃t�H�[���ŋL�����������̂��B���ʂ͉��t�ւ̏d�v�Ȏ�|���肾���A�Ȃ��̂��̂ł͂Ȃ��B
�o���h�����K����Ƃ��́A����̃p�[�g�͎����̒��Ŕ[���ł����ԂŏW�܂�A�o���h�Ƃ��ċȂ��ǂ��d�グ�邩�Ƃ����R�~���j�P�[�V���������Ƃ����B�����āA�����̉��t�Ɏ��M�����Ă�܂Ŏ�����K��ς�ł��̏�ɗՂ܂Ȃ��ƁA���̃����o�[�ƃR�~���j�P�[�V���������]�T���Ȃ��Ȃ�B�����̂��ƂŐ���t�ɂȂ�B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�őg�D�}�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���d�v�Ȃ̂͐}�ł͂Ȃ����̂ł���B�}�͂����܂ł��A�l�X�����ʂ̃C���[�W�����Ƃɘb���������ł���悤�ɁA�g�D�̂���������ȒP�ɕ\�������̂ɂ����Ȃ��B��
�g�D��v�i�f�U�C���j����Ƃ��́A�v�}�Ƃ��Ă̑g�D�}���K�v���B�g�D�}�͇@�Ј������ʂ̃C���[�W�����Ƃɘb���������ł���A�A�g�D�̂���������ȒP�ɕ\���A���̂ł�������B��ɂ��ׂ��͑g�D�}������ɂ������ƂłȂ��A�g�D�S�̂̓������Ɗe�Ј��̓������i�Ȃ̑S�̑��Ɗe�p�[�g�̉��t�j���V�~�����[�V�������邱�Ƃ��B
�Ј����g�D�}�����āA�g�D�S�̂ʼn����������āi�ȑS�́j�A�����ɋ��߂��Ă���̂͂ǂ�ȓ������i�����̉��t�j�����A���ɑz���ł���B���̗����̐[���͖��ł͂Ȃ��B�����Ȃ�ɂ������������Ǝv���邱�Ƃ��d�v���B�����̃p�[�g�͂Ƃ肠���������̂��̂ɂ����Ɗm�M�ł���B�����Ɏ��M�������āA���킸�Z�b�V�����ɗՂ߂��Ԃ��B
�����o�[�������Ɏ��M�������Ďd���ɗՂ߂邩�ǂ������A�`�[���Ƃ��ăp�t�H�[�}���X���ł��邩�ǂ����̕�����ڂ��B�����Ɏ��M������Ƃ��́A�S�ɗ]�T�����܂��B���҂̂��Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���B�����Ɏ��M���Ȃ��Ƃ��́A�����̂��Ƃ��l���邾���Ő���t�ɂȂ�B���҂̂��Ƃ��l����]�T���Ȃ��Ȃ�A���Ȓ��S�I�ɂȂ��Ă��܂��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ńv�����j���O�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���Ɩ��̒S����̍s����j�[�Y��m���������Ńv�����j���O���s��Ȃ�������A���̒��g�͊���ł͂����Ɋ����������Ƃ��Ă��A�����Ď��s����Ȃ����낤�B�t�ɁA�Ɩ��̒S����̑��ł��v�����j���O�S���҂̈Ӑ}�𗝉����Ă��Ȃ���A���ʂ������Ȃ����A���邢�́A���߂��鐬�ʂɑ��āu�����ɍ���Ȃ��v�u����Ɍ��߂�ꂽ�v�u�n���炵���v�ȂǂƔ������邾�낤�B��
�g�D�̎��̂�v����Ƃ��́A�o�c�w������I�ɍl���ĎЈ��ɒ��Ă����܂������Ȃ��B���ۂɋƖ���S���Ă���Ј��̈ӌ����Ȃ���A�ꏏ�ɂ����Ă����v���Z�X������B�o���h�̃~���[�W�V�����́A���݂��ɃI���W�i���̃t���[�Y��������Ă����v���Z�X�ŁA�ȑS�̂Ǝ����̈�̊�����B�A�����W���P�O�O���w��ł͂��C�͎�����B����Ȃ玩���łȂ��Ă������B
�g�D�͐l�̏W�܂�Ƃ��āA���X�ω��������Â���B�ЂƂ̑g�D���u���������g�D���v�ƌ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�Ԃ��Ƃɗl�X�ȕ\��������B���̑g�D���Ȃ�Ƃ��\�����悤�Ƃ���ƁA�ǂ�����ʂ���邵���Ȃ��B�g�D�}��x�͂����������̂��B������A�g�D�́u���v�ɍ��킹�āA�g�D�}��x�́u�Áv�����킹�Ă����B������J��Ԃ��A�����������m���Ɂu���v�Ɓu�Áv���Z�����Ă����͂����B
����͑g�D�K�w�ƒm���J���҂ɂ��čl���Ă����\��ł��B�m2014�N4��1���n
�w�u�S�̂ƕ����v�Ƒg�D�}�l�W�����g�i��j�x�@�ivol.11�j
�u����A�܂�����ڕW��悹�������H�v�u�������A�N�Ȃ�ł���B�撣���Ă��ꂽ�܂��B�v�u��������l�𑝂₵�Ă��������B���̃����c������E�ł��B�v�u�������A�킩�����B�l����͌��������V�l���ЂƂ����悤�B�����̖ڕW�B���͗����B�v
�u���[�A�N�����҂̐V�l�N���B�N�Ȃ�ł����B�撣���Ă��ꂽ�܂��B�v�u�͂��A�ꐶ�����撣��܂��B�����킩��Ȃ��̂ňꂩ�炲�w����낵�����肢���܂��B�v�u�����A���͖Z�����Ď��Ԃ��Ȃ��B�Ƃɂ��������g���ē����̂��c�Ƃ�����ȁB�v
�u����A�����̏��k�̓^�t�������ȁB�ł������������Ă邼�B���ꂩ���̖�A�O�̖���ǂ������Ă������A�܂��O�鑱�����ȁB���`�A�Z�����B�v�u���������ΐV�l�N�A�c�Ƃ̐��ʂ͂ǂ����H�v�u��ď������Ă܂��B�v�u���Ⴄ��B�����g���A�����B�v
�u����Ȃ��ƌ����Ă��A�����Ȃ�K��Ȃ�Ė���������B�v�u���`��A������������ȁB�Ƃ肠�����N����������ď��������Ă���B�v�u�����A����͂����B�V���v�����_���I�Ő����͂�����B�v�u�ł��l�Ɖ���Ęb���̂����Ȃ�ˁB�v
�����Ƒ��҂͈Ⴄ�Ƃ������Ƃ�{���ɗ����ł���l�͂܂ꂾ�B�l�͎����̐��E�������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A���҂��������E�����Ă���Ɩ��ӎ��Ɏv���Ă���B�����玩���̊�ő��҂𗝉����Ă��܂��͖̂������Ȃ����Ƃ��B�������ł��邱�Ƃ͑�����ł���Ƃ����v�����݂͋����B�H���u�Ȃ�łł��Ȃ��H�ȒP����B�v
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ől�̋��݂ɂ��Ă��������Ă��܂��B
�����ʂւ̈ӗ~��|�����߂ɂ́A�ЂƂ�ЂƂ�ɋ��݂𑶕��ɔ���������K�v������B�l�ނ̎�݂ł͂Ȃ��A�����܂ł����݂ɗ͓_��u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��
�C�M���X�̌o�ϊw�҃��J�[�h�͒����w�o�ϊw�Ɖېł̌����x�ŁA���R�f�Ղ́u��r�D�ʐ��v��������B�Q�̓������i�Y���Ă���`���Ƃa��������Ƃ���B�`���͂a�����Q�̏��i�Ƃ����Y���������B���̏ꍇ�ł��A�`���Ƃa�����e�����Ő��Y�����������̏��i�ɓ������Đ��Y����A�����S�̂Ő��Y�ʂ�������Ƃ��������B
���J�[�h�͉p���ƃ|���g�K���̗��������B�p���͕z�n�P�P�ʂ̐��Y�ɔN�ԂP�O�O�l�A���C���P�P�ʂ̐��Y�ɔN�ԂP�Q�O�l�̘J�����K�v�ŁA�|���g�K���͕z�n�P�P�ʂ̐��Y�ɔN�ԂX�O�l�A���C���P�P�ʂ̐��Y�ɂW�O�l�̘J�����K�v���Ƃ���B�i�z�n�P�P�ʂƃ��C���P�P�ʂ́A���ێs��œ������l�����Ă���Ƃ���j
�|���g�K���͕z�n�ƃ��C���̂�������p����萶�Y���������̂ŁA�p���ɑ��āh��ΗD�ʁh�ł���B����p���͕z�n�ƃ��C���̂�������|���g�K�����h��Η�ʁh�ł���B�h��r�D�ʁh�͂P���̒��Ŕ�r���đ��ΓI�ɐ��Y�������������w���B�p�����ł͕z�n�����C���ɑ��āh��r�D�ʁh�������A�|���g�K�������ł̓��C�����z�n�ɑ��āh��r�D�ʁh�����B
���ꂼ��̍��̒��Ŕ�r�D�ʂ������Y�ɓ������邱�ƂŁA�S�̂Ƃ��Đ��Y�ʁi�f�c�o�j���ő�ɂ��邱�Ƃ��ł���B�p�����N�ԂQ�Q�O�l�ŕz�n�Y����ƂQ�D�Q�P�ʂł���B�|���g�K�����N�ԂP�V�O�l�Ń��C���Y����ƂQ�D�P�Q�T�P�ʂł���B��������O�́A�������킹�ĕz�n���Q�P�ʁA���C�����Q�P�ʂ��B�f�Ղɂ�藼���Ƃ��ȑO��葽���̐��Y�邱�Ƃ��ł���B
���{��J�������O�Ɉړ����Ȃ��O��Ȃ̂ŁA�Y�Ƃ̋�������錻��ɂ͍���Ȃ�����������B�����͑O�����������o�σ��f���̌��E��F�����āA���܂��g�������B����l�A���Y�����d���ƒu��������Ƒg�D�}�l�W�����g�̃q���g�������Ă���B
�}�l�W���[�͌ڋq���P�O���K�₷��̂ɂR���ԁA��ď����P�����̂ɂT���Ԃ�����Ƃ���B�V�l�͂P�O���̖K��ɂP�O���ԁA�P���̒�ď��ɂU���Ԃ�����Ƃ���B�}�l�W���[�͐V�l�ɑ��āh��ΗD�ʁh�ŁA�V�l�̓}�l�W���[�ɑ��āh��Η�ʁh�̊W���B
���R�����}�l�W���[�̕�����ΓI�Ɏd���̃p�t�H�[�}���X���悢�B���ł������ł�����ق������܂������ƍl����͎̂��R���B�������g�D�S�̂ł݂�ƁA���ꂼ��̃����o�[���h��r�D�ʁh�i�����݁j�ɓ������邱�ƂŁA�S�̂Ƃ��ẴA�E�g�v�b�g��������B
�l�d���łQ���ԒP���ɉ߂����ƁA�}�l�W���[�͂Q�O���̖K��ƂQ���̒�ď��A�V�l�͂P�O���̖K��ƂP���̒�ď��ƂȂ�B�S�̂Ƃ��ĂR�O���̖K��ƂR���̒�ď����B�}�l�W���[�����g�̔�r�D�ʂł���ڋq�K��ɓ������A�V�l����������ď��쐬�ɓ������ĂQ���ԉ߂����ƁA�S�̂Ƃ��ĂT�R���̖K��ƂR���̒�ď��ƂȂ�B
�g�D�S�̂Ƃ��Ă��ꂼ�ꂪ���g�̔�r�D�ʂɓ������邱�ƂŁA��ď��쐬�̐������炳���ɖK����P�R�����₷���Ƃ��ł����B�����āA���ꂼ�ꂪ���������d���ɏW������ΐ��Y�����オ��i���݂���苭������j�A�g�D�S�̂̃A�E�g�v�b�g�������Ă����B
�l���ꂼ��Ɍ������邩�琢�̒��������낢�B�l�ɂ���ċ��݂��݂��Ȃ�������A���݂��݂��R���R���ς���Ă̓A�C�f���e�B�e�B���낤���Ȃ�B���̐l�̋��݂��݂́A���������ς����̂łȂ��ƌo���͋����Ă����B�܂��A�l�̋��݂Ǝ�݂̂ǂ����悤���Ȃ������́A����s����Ƃ����������̂ق����D�ɗ����邩������Ȃ��B
��r�D�ʐ��͐��Y�ʂ���ɂ��Ď��ɐG��Ă��Ȃ��̂ŁA�K����ď��̎��͂ǂ��ȂƂ����c�b�R�~�����ꂽ���Ȃ�B�������A�l�Ԃ͂��܂����𑪂镁�ՓI�Ȓm�b���������ĂȂ��B�����A����ł�����̂͑傫�Ȏ�|����ɂȂ�B�����邩����̎�|�����T�����Ƃ��A�������ɋ߂Â����Ƃ��B
����M��������Ƃ��鎞�_�i�����_�j�œˑR�C�̂Ɏp��ς���悤�ɁA���R�E�ł́h�ʂ����ɕς��h�Ƃ����u�Ԃ�����B�ʂ����Ȃ��Ă͂��߂āA���������Ă��邱�Ƃ�����B�u�Ȃ��g�D�S�̂̐��Y�����グ�邽�߂ɐl�̋��݂����̂��v�Ƃ����₢�ɑ��āA��r�D�ʐ��͋�̓I�ȃq���g��^���Ă����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ől�ނ̋��݂Ɛ��Y���ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���l�ނ́A���݂�ʂ�������\���Ɋ��҂��Čق��͂��ł���B�g�D�̑_���́A������̋��݂��e�R�ɂ��Đ��Y�������߁A�l�ނ̎�݂ɂ�鈫�e�������킷���Ƃɂ���B��
�����������A�l�ނ͎�݂��������߂Ɍق����̂ł͂Ȃ������B�����̑g�D�ł́A�Ȃ����l�̎�݂Ƀ_���o���ĉ��P�����߂Ă��邱�Ƃ������B�l�͑��҂̌��_�͂悭�����邪�A���݂͌����ɂ����B�}�l�W�����g�͂����Đl�̋��݂����ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����͑g�D�f�U�C���̕��@�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�@�m2014�N3��17���n
�w�u�S�̂ƕ����v�Ƒg�D�}�l�W�����g�i�O�j�x�@�ivol.10�j
�u���ꂪ�P�~�߂̖�ł��B���ꂪ�A�̒ɂ݂��Ƃ��ŁA�������͔M���������ł��B�����͖�͈݂��r�炷�̂ŁA�����}���邽�߂̈ݖ�ɂȂ�܂��B�v���ׂ��Ђ��ĕa�@�ɍs�����Ƃ��A�悭�����ǂł̉�b���B�����A�ݖ���Ă����������̂Ȃ́H�Ƌ^����������ꂽ�Ƃ���Ɉ���ł݂邪�A��̂������ŕ��ׂ����邱�Ƃ͂܂ꂾ�B
���ׂ�������������a�@�ɍs�����̂ɁA�h�P���~�߂�h��h�A�̒ɂ݂��Ƃ�h��h�M��������h�ȂǁA���ׂɂ���Č����X�̏Ǐ���������邱�Ƃɖ�肪����ւ���Ă���B���ׂ��������ƂƁA���ꂼ��̏Ǐ���������Ƃ͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����B���ׂ͊e�Ǐ�̏W�܂�Ƃ��������A�g�̑S�̂����ׂ̏�ԂɂȂ��Ă��銴�o���B
�g�̑S�̂Ƃ����V�X�e�������炩�̕s����N�����āA���ׂƂ����g���u���������N�����Ă���Ƃ��������B�l�Ԃ̐g�̂́A�ܑ��Z�D�h�Ƃ��������h���琬��g�́h�S�́h�̃V�X�e�����B���ꂼ��̑���͕ʁX�Ɏ���̖����𐳂����ʂ����A���X�ƕω�������ɑΉ����āA�g�̑S�̂�����ɋ@�\���邱�Ƃ�ڎw���āA���݂����▭�ɘA�g���Ă���B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�őS�̂ƕ����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���S�̂̐��ʂƌʋƖ��Ƃ�����̌����̊Ԃɂْ͋��W�����܂��B���ْ̋��W�������ւƓ����A��������ʎ��ݏo���̂��A�}�l�W�����g�ɂƂ��ĕs�f�̖��߂ł���B��
���ׂɂ��g�̂̊e�����̏Ǐ�ƁA���ׂ��Ђ��Ă���Ƃ����g�̑S�̂̏�ԂƂ̂������́A�����ƌ��ʂ̊W�Ƃ������́A���݂��ْ̋��W�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�g�̑S�̂��ЂƂ̃V�X�e���Ȃ�A�X�ɏǏ���������悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�V�X�e�����@�\���Ȃ��{�g���l�b�N�̂悤�ȍ��{�̌�����T���āA������e�R���ĉ�������l����B
�}�l�W�����g�̋@�\�̂ЂƂ́A��Ƃ̖ړI�Ǝg���m�ɂ��āA�l�����≿�l�ς̈قȂ�l�X�������Ɍ����킹�邱�Ƃł������B�������A�ЂƂ�̐l�Ԃ������Ă���l�����≿�l�ς́A���ꂼ�ꂪ�Ⴄ���ō����܂Ő����Ă��Ē~�ς��ꂽ���̂��B���̍l�����≿�l�ς�ς��邱�Ƃ́A���܂Ő����Ă������ԂƓ��������K�v��������Ȃ��B
��Ƃ̖ړI��g���m�ɂ��邱�Ƃ́A�}�l�W�����g�̎n�܂�ł���O�B�����āA�ړI��g���m�ɂ��Ă͂��߂āA�ЂƂ�ЂƂ�̎Ј��Ƃْ̋��W���\�ʂɌ���Ă���B�ْ��W�������邱�Ƃ́A���݂��̍l�����≿�l�ς̈Ⴂ�������邱�Ƃ�����A���̈Ⴂ���肪����ɂ��āA���݂��ɑΘb�����ݍ��킹�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŃR�~���j�P�[�V�����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���R�~���j�P�[�V�����́A���ʂ̗����⌾�t��O��Ƃ��Ă��邪�A�����Ă��̏ꍇ�A���ꂱ�����܂��Ɍ����Ă���̂ł���B��
��Ƃ̖ړI�Ǝg���m�ɂ�����A������S���ŏ������Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł͖{���ɗ�������邱�Ƃ͂Ȃ��B���t�ɂ͌`���ƈӖ�������B���@�㐳�����\�ʏ�̌��t�����L���邱�Ƃ͂ł��邪�A���t�͂��ꂪ�w�������Ӗ��Ə�ɃZ�b�g���B�Ӗ������L����Ȃ�������A�{���ɗ��������L���ꂽ���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�l�͈Ӗ��������ł��Ȃ��܂܁A����ϋɓI�ȍs���Ɉڂ����Ƃ͓���B��Ƃ̖ړI�Ǝg���ɂ��āA���̈Ӗ��̗�����g�D�S�̂ŋ��L���邽�߂ɁA�Ӑ}�I�ɃR�~���j�P�[�V�����̂����݂����邱�Ƃ��A�}�l�W�����g�̕��@�̂ЂƂƂ����������B
����͈��������u�S�̂ƕ����v�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�@�m2014�N3��3���n
�w�}�[�P�e�B���O�Ǝ��Ђ̎��Ƃ͉����Ƃ����₢�x�@�ivol.9�j
�u�ߑO���Z����������ł����������Ȃ��A�߂��Ƀ��[�����������邩����邩�H�v�����������������Ƃւ́h�j�[�Y�h���B�u�����̒��H�͕���ł�����������A�v���Ԃ�Ɂ������̃��[�������H�ׂ����Ȃ��I�v���ł͂Ȃ��������̃��[�����ւ́h�E�H���c�h���B
�R�g���[�͒����w�}�[�P�e�B���O�E�}�l�W�����g�x�Ńj�[�Y�ƃE�H���c�̈Ⴂ�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���j�[�Y�Ƃ́A�H���A��C�A���A�ߕ��A���J�������ꏊ�Ƃ������l�Ԃ̊�{�I�~���ł���B���������j�[�Y�������������̂��̂Ɍ�������ƃE�H���c�ɂȂ�B��
�J��Ԃ������Ă����u�ڋq���t�@���v��n�����邽�߂ɂ́A���Ђ̏��i��T�[�r�X���l�X�̃j�[�Y���������ł͂��̑���Ȃ��B���̏ꍇ�͐������̋������Ђ̒�����A���ʂȗ��R���Ȃ����̂Ƃ��ɑI�ꂽ�\���������B�u���ꂪ�~�����I�v�Ƃ����E�H���c�������i������Ƃ��ɁA���ꂩ�璷���t�������ɂȂ�ڋq�����܂꓾��B
���Ђ̌ڋq��n�邱�Ƃ��ł��A�ڋq�̃E�H���c�������i��T�[�r�X��������邱�Ƃ��ł����Ƃ��A���̊�Ƃ͉�����ɓ��ꂽ�ƌ����邾�낤���H�ЂƂ̃u�����h����ɓ��ꂽ�Ƃ����邾�낤�B�ڋq�͎����̂��C�ɓ���̃u�����h���w����������B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ń}�[�P�e�B���O�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���}�[�P�e�B���O�̑_���́A�̔��w�͂�s�v�ɂ��邱�Ƃł���B�ڋq��m��s�����������ŁA�������Ȃ��Ă�����Ă����悤�ȁA�ڋq�ɂӂ��킵�����i��T�[�r�X�����̂��A�}�[�P�e�B���O�̖ڎw���Ƃ���ł���B���z�́A�}�[�P�e�B���O�̌��ʁA�ڋq���i��ŏ��i���w�����Ă���邱�Ƃł���B��
�u�����h�Ƃ́A�u�ڋq�ւ̒��l�̖v�ƒ�`�ł���B�ڋq�������̊�Ƃ̏��i��T�[�r�X���Ă��A�����������鉿�l�▞���𗠐�Ȃ��ƈ��S�ł���M���W�̂��Ƃ��B����j�[�Y�ɑ��ď��i��I�ԂƂ�����Ƃ͂���Ȃ�ɕ��S�ɂȂ�B����҂������Ƃ̌ڋq�ɂȂ邱�Ƃ́A��Ƃƌڋq�̑o�����ڎw���ׂ��S�[���Ƃ������������B
���Ƃ��A�������̌ڋq�͏��i�Ƃ��Ẵ��[������~���Ă���̂��낤���H���[�����̖���f�ނɂ���������Ă��邾�낤���A���X�̕��͋C������A�叫�̐l����X���̐ڋq�A�������o�����ԓ��X�A�����Ɖ��i���r���Ȃ��牿�l�������Ă���͂����B
�����ւ��āu���Ђ̎��Ƃ͉����H�v�̖₢�ɓ����邽�߂̏������ł����B���Ɂu�ڋq�͎��Ђ̉��ɉ��l�������Ă���̂��H�v�ɓ�����B����������邱�Ƃ��ڋq��n�����邱�ƁA�܂莩�Ђ̖ړI��g���A�u���Ђ̎��Ƃ͉����H�v�ւ̓����ɂȂ�B�u���Ђ̎��Ƃ͉����H�v�ɓ�����ɂ́A��Ɂu�ڋq�͒N���H�v�ɓ�����K�v���������̂��B
�u���Ђ̎��Ƃ͉����H�v�ւ̓����͎��Ђ̖ړI��g���ł���A���Ђ����݂���Ӗ�������A���ׂĂ̎Ј��͂����Ɍ������Đ��ʂݏo�����߂Ɍٗp����Ă���Ƃ������Ƃ��B�g�D���}�l�W�����g����Ƃ́A���Ђ̖ړI��g���Ɍ������ĖڕW�Ƃ��鐬�ʂݏo�����߂ɁA�Ј��ЂƂ�ЂƂ�̐��ݗ͂��ő�Ɉ����o�����g�݂Ƃ�����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ŏ��Ђ̎��Ƃɂ��Ă��������Ă��܂��B
���u���Ђ̎��Ƃ͉����A�������Ƃɂ��ׂ����v�Ƃ����₢�̓�����N�����g���Ă���̂��B�i�����j�g�D�̑S�������ʂ̃r�W�����ƔF���������A�����𑵂݂��ēw�͂��邽�߂ɂ́A�u���Ђ̎��Ƃ͉����A�������Ƃɂ��ׂ����v�����߂邱�Ƃ��������Ȃ��B��
�ЂƂ�ЂƂ�̎Ј������Ђ̖ړI��g���ɂ��ĈقȂ铚���������Ă��邱�Ƃ́A�l���S�ē����l�����ł��邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ�����A���R�̂��Ƃ��B�}�l�W�����g�́A�g�D�ɋ��ʂ̖ړI�Ǝg�����߂�Ƃ������@���g���A���̊�Ƃ̈���Ƃ��ē������Ԃ͑S���������Ɍ����킹��Ƃ����@�\���ʂ����B
����͑g�D�}�l�W�����g�̕��@�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�@�m2014�N2��17���n
�w�ڋq�͒N���Ƃ����₢�ƃ}�[�P�e�B���O�x�@�ivol.8�j
�u�����邳��K���o���`�v�u�����N�������K���o���`�v�A�}���\�����łЂƂ��퉞�����W�߂�̂��R�[�X���ʂ�R�X�v�������i�[���B�ӂ��R�X�v���Ƃ����Ǝ������D���Ȑl����A�j���̃L�����N�^�[�̈ߑ����܂Ƃ����Ƃ��������A���Ƃ��Ƃ��錾�t��"costume
play"�͉����p��ŁA�Â�����̈ߑ��𒅂ď㉉���錀�̂��Ƃ������B
"custom"�A"costume"�A"customer"�͓����ꌹ���B"custom"�́u�K���A���K�A���s�v�A��������hcostume"�́i���邱�Ƃ��K���ɂȂ��Ă��镞�Ƃ��Ắj�u�ߑ��v�ƂȂ�A"customer"�́i���̂��X���甃�����Ƃ��K���ɂȂ��Ă���l�Ƃ��Ắj�u�ڋq�v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�u�ڋq�v�Ƃ́A����n��̖����Ɩ����ߑ��Ƃ̊W�̂悤�ɁA���̂��X���甃�����Ƃ������Ԃɂ킽���ďK���ɂȂ��Ă���l�̂��Ƃ��B��������Ɓu�ڋq���l���iget�j����v�Ƃ����������ɂ́A��͂��a��������B�l���iget�j���邱�Ƃ��ł���̂́A�ڂ�C�ŏu�ԓI�itemporaly�j�ȁu����ҁv�Ƃ������������������肭��B
�u�ڋq�̑n���v�Ƃ́u�ڋq����V���ɑ���v���Ƃł������B���X�̏��i�𖢂����������Ƃ��Ȃ��l���A���̂��X���甃�����Ƃ��K���ɂȂ����l�ւƕς���v���Z�X�Ƃ�����B����������A�u���s�[�^�[�v������o���A�u�t�@���v��u�T�|�[�^�[�v�Ɉ�ďグ�āA�������I�Ɍp�����ė��v�������邱�Ƃ���Ƃ̖ړI���B
�u�ڋq�͒N���v�̖₢�́u�ǂ�Ȑl�����Ђ́i���i��T�[�r�X�́j�t�@����T�|�[�^�[�ɂȂ肤�邾�낤���H�v�u�ǂ�Ȑl�����Ђ́i���i��T�[�r�X�́j�t�@����T�|�[�^�[�ɂ��������H�v�ƌ�����������B�����āA���Ђ̃t�@����T�|�[�^�[�ɋ��ʂ�������𑨂��邱�Ƃ��A�u���Ђ̌ڋq�v�̊T�O�𑨂��邱�Ƃ��Ƃ�����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ŋ�Ƃƌڋq�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
����ƂƂ͉��������߂�̂͌ڋq�ł���B�ڋq�������A���i��T�[�r�X�ɑΉ����x�������Ƃ����ӎv�������Ƃɂ��A�o�ώ�����x�ցA�����ĒP�Ȃ郂�m�����i�ւƕς���B��
���Ƃ��A���̃~���[�W�V�������u���ɂ̃T�E���h���A�N�������̍������y���ł����I�v�Ɩi���A���Ƃ����ꂪ�{���������Ƃ��Ă��A����������Ǝv���t�@�����ЂƂ�����Ȃ���A���ƓI�ɂ́u�P�Ȃ�I�g�v�ɂ����Ȃ��B�ڋq�����܂�Ȃ���A�ނ͐E�ƃ~���[�W�V�����ɂȂ�Ȃ��B�ڋq�������u���́v����邱�Ƃ��ł���B
�h�J�b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ń}�[�P�e�B���O�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
���^�̃}�[�P�e�B���O�Ƃ́A�����肨��т��̐l�����ԁA����A�j�[�Y�A���l�ςȂǂ��o���_�Ƃ�����̂��B�u���������͉��肽�����v�ł͂Ȃ��u���q�l�͉��������ƍl���Ă��邩�v�Ɩ₢�A�u���ꂪ���i�E�T�[�r�X�̗p�r�ł��v�ł͂Ȃ��A�u���q�l���T�����߁A�d�閞���������ɂ���܂��v�Ƒi����B��
�E�ƃ~���[�W�V�����́u�����͉�����肽�����v�ł͂Ȃ��u�t�@���ɂȂ�l�͉��������ƍl���Ă��邩�v�A�u���ꂪ�l�̉��y�ł��v�ł͂Ȃ��u�t�@���ɂȂ�l���T�����߁A�����ł��鉹�y�������ɂ���܂��v�Ƒi����B�����̂�肽���Ȃ����y�ł��A�ڋq�����߂���̂����Ȃ���Δ���Ȃ��B�ڋq��n������Ƃ͂����������Ƃ��B
�u�ڋq�����߂Ă�����̂��ł����I�v�Ƌ���ł݂Ă��A���ꂪ�ڋq�����߂Ă������̂��ǂ����́A���ۂɌڋq�������Ă����܂ł킩��Ȃ��B���l�̐S�̒������邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A�ڋq�����߂Ă�����̂͑z�����邵���Ȃ��B�������Ȃ����牼��������B�����ƌ����J��Ԃ��Ă����A�u�ڋq�Ƃ͒N���v�������т������Ă���͂����B
����͈��������}�[�P�e�B���O�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�@�m2014�N2��3���n
�w�ڋq��n�����邱�Ƃ͌ڋq���l�����邱�Ƃ��x�@�ivol.7�j
�u�����̐V�K�ڋq�̊l���ڕW�͂P�O�l�����A�C��������Ă����I�v�u�킩��܂����A�撣��܂��I�v�B�|��Ɓu���ق��Ă���������A����Ȗ�������Ȃ��ł�v�ł��邱�Ƃ������B�ڋq���l������͓̂���B�c�Ƃ���������Ƃ�����҂Ȃ�A���̎������g�̂ɍ��܂�Ă���͂����B
�ڋq���l������Ƃ����̂́A�ڋq���h�������h����Ƃ����C���[�W���B�u���v������|�R�X�g�v�ł��邩��A��Ƃ����v�������邽�߂ɂ́A�R�X�g�ɍ���������锄�オ�Ȃ��Ă͂͂��܂�Ȃ��B�R�X�g�͊�Ƃ̒��Ő��܂�邪�A����͊�Ƃ̊O�i���ڋq�j���炵�����܂�Ȃ��B�����玩�R�ȗ���Ƃ��āA����������邽�߂Ɂu�ڋq���Q�b�g����v�Ƃ������z�ɂȂ�B
��Ƃ͖@�l�Ƃ����l�i��@���ŗ^�����Ă���悤�ɁA�l�ԂɎ������݂Ƃ��đ������Ă���B��Ƃɑ��čD�������̊�������̂��A���̊������l�Ƃ��Ă̊����Ɋ����邩�炾�B�H�ב����Ȃ���ΐl�͐����Ă����Ȃ��悤�ɁA�ڋq���l���������Ȃ���Ί�Ƃ͐����Ă����Ȃ��B�ڋq�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����A���̊�Ƃ̎������s����Ƃ����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ŋ�Ƃ̖ړI�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
����Ƃ̖ړI�͂��ꂼ��̊�Ƃ̊O�ɂ���A�������ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B��Ƃ��Љ�̈ꕔ�ł���ȏ�A���̖ړI���܂��Љ�ɂ���B��Ƃ̖ړI�Ƃ��đÓ��Ȓ�`�͂����ЂƂ����Ȃ��B����́A�u�ڋq��n������v���Ƃł���B��
�ڋq���l���i�������j����ƌ������Ƃ��A���̍l���̒��S�ɂ���̂͊�Ǝ������g���B��ƂɌڋq���K�v������ڋq���Q�b�g����B���̂Ƃ���Ƃƌڋq�̊W�́A��ł̐l�Ɗl���Ƃ̊W�̂悤�ɑΗ��W�ɂ���B����̖ړI��B�����邽�߂�㩂�����������m�b���i��Ȃ���A�l�����Q�b�g����B�ړI�͓������ł���B
�ړI���������A�܂莩�Ȓ��S�I�Ȋ�Ƃ��D����邱�Ƃ͂Ȃ�����A�Љ�ő��݂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ŁA�ڋq���l���ito ������ a customer�j����̂ł͂Ȃ��A�ڋq��n���ito
������������ a customer�j����B�������A�����������̂��B��������c�ƖڕW�́u�����̐V�K�ڋq�̑n���ڕW�͂P�O�l�v�ɂ��悤�B�����A�Ȃ�̂�������B
�L�����Łu�n���v�������Ă݂�ƁA�u�@�V���ɑ��邱�ƁB�V�������̂�͂��߂邱�ƁB�A�_���F���邱�ƁB�v�Ƃ���B�Ȃ�قǁA�ڋq�͖�����V���ɑ�����̂��B�X���s�������l�X�͊F�ڋq�ɂȂ肻���Ɍ����邪�A�����ł͂Ȃ��B�X���s�������l�X�͂��łɂ������݂��邪�A�ڋq�͐V���ɑ����Ă͂��߂đ��݂���B�l�X�ƌڋq�Ƃ����T�O���čl���邱�Ƃ��J�M�̂悤���B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ŋ�Ƃ̖ړI�Ǝg���ɂ��Ă��������Ă��܂��B
����Ƃ̖ړI�Ǝg�����l���邤���Ő^����ɍl����ׂ��K�{�̖₢�́A�u�ڋq�͒N���v�ł���B���̓����͂��悻�����ł͂Ȃ��B����ɂǂ������邩�ɂ���āA��Ƃ����Ђ��ǂ���`�Â��邩�������ނˌ��܂�B��
�u�ڋq�͒N���iWho is the customer?�j�v�ƕ������A�u�����ƁA�`�Ёi����j�Ƃa�Ёi����j�Ɓc�v�Ɠ�����̂����ʂ��낤�B���̓��������Ƃ̖ړI��g���͓����o�������ɂȂ��B�������A�ʂ̉�Ђ�l�ł͂Ȃ��A�ڋq�Ƃ����T�O�𑨂��邱�Ƃ��ł���A�K�ȓ������o���������B
����̓}�[�P�e�B���O�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�@�m2014�N1��20���n
�w���ʂ������邱�Ƃ͗��v�������邱�Ƃ��i��j�x�@�ivol.6�j
���{��Łw�}�l�W�����g�x�̒��Łu���ʁv�́A�����́uperfomance�v�̖��Ƃ��Ďg���Ă���B�u�����̉��Z�͂����p�t�H�[�}���X�������ˁv�Ƃ͌����Ă��A�u�����̉��Z�͂������ʂ������ˁv�Ƃ͌���Ȃ��B�uperform�v�̌ꌹ�́Aper�i���S�Ɂj�{form�i�������j���u���S�Ȍ`�ɂ���v�ŁA��͂�h���b�J�[�̌����u���ʁv�́A�u���ʁv���̂��̂ł͂Ȃ��A�u���ʂ��`�Â���v���Ƃ��Ӗ����Ă���悤���B
���v�̌���������o�����Ƃ��}�l�W�����g�ł���Ȃ�A�u���̂��߂Ƀ}�l�W�����g����̂��v�Ƃ����₢�́A�u���v�Ƃ͉����v���l���邱�ƂƓ������B���v�Ƃ͊�Ƃ��p�����A�������邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂ł���B���̒ʂ肾�B�������悭�l����ƁA��Ƃ����ݏo�����v�Ƃ́A�o�ώЉ�𐬂藧�����邽�߂̗B��̌���ł��邱�Ƃ��킩��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�Ŋ�ƂƗ��v�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
����Ƃ͌o�ϐ��ʂނ��߂ɑ��݂��Ă���A���ꂪ��Ƃ̒�`�ł���B�i�����j��Ƃ��Љ�ɂ����ĉʂ����ׂ��w�߂́A�����Čo�ς̐��ʂ����ł͂Ȃ����A�o�ς̐��ʂ������ł��d�v�ȓw�߂ł���B�Ȃ��Ȃ狳��A�ی��E��ÁA�h�q�A�m���̑��i�Ȃǂق��̂��ׂĂ̎Љ�I�w�߂́A�o�ώ����̗]��A�܂藘�v�Ȃǂ̗��ۂɈˑ����Ă���A����ݏo���ɂ͊�Ƃ��o�ς̐��ʂ�������ȊO�ɕ��@���Ȃ��̂��B��
���ƍ����Ƃ����ƁA���Ƃ��Ε⏕���Ȃǁu��������炤�v�Ƃ������o�ɂȂ��Ă��܂����A���Ƃ��������i�l�̋��^����Ƃ���x������̂Łj��Ƃ̗��v����x����ꂽ�ŋ����B���ł܂��Ȃ��Ă��镪�́A�����̗��v�����Ăɂ������̂��B���ł��Ă����肪�Ȃ���Ε����Ȃ��̂�����A�Љ�̓}�l�W�����g�������Ɋ�Ƃ̗��v���������邩�ɂ������Ă���B
�Љ�ɂƂ��Ắu���v�Ƃ͉����v�͕��������B�ł͊�ƂɂƂ��Ắu���v�Ƃ͉����v�́A���������L�ł��Ă���̂��낤���B�u���v��������Ƃ́H�v�ƕ����ꂽ��A�u�ׂ��邱�Ƃł���v�Ɠ�����B�܂�������a���̂Ȃ���b���B�ł�������Ǝv�l��~���ȃ��o����������B
���W�J���V���L���O���悤�B�u�r���@�v�������H�v�i����ŁA�ׂ��Ăǂ�����́H�j�B����ɂ����������ƁA�ӊO�Ƃ����܂ōl���Ă��Ȃ��������ƂɋC�Â��B�u�ׂ���܂����H�v�u�ڂ��ڂ��ł�ȁv�B�ׂ��邱�Ƃ͂悢���Ƃ��A���傠�邩�B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŗ��v�̖����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
�����v�̎Љ�E�o�ϖʂł̖����́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B�P�D���ƌp���R�X�g��d�����߂́u���X�N�v���~�A���i��悹���v�j�v�A�Q�D�����̌ٗp��d�����߂̎��{�̌���A�R�D�C�m�x�[�V�����ƌo�ϐ������㉟�����邽�߂̎��{�̌���
�O��̃R�����ŁA���v�͕s�m���ȏ����ւ̃��X�N����������^�[���Ƃ������߂��ł����B����Α����猩��ƁA�����̃��X�N����邽�߂ɕK�v�ȕ��̗��v�����߂���Ƃ������Ƃ��B����̑傫���ɔ�Ⴕ�āA��邱�Ƃ��ł��郊�X�N�̑傫�������܂��Ă���B�ł͏����ǂꂾ���̃��X�N����낤�Ƃ���̂��A��������߂邱�Ƃ��}�l�W�����g�̖����̂ЂƂƂ����������B
����}�l�W�����g�̕��@�ɂ��čl���Ă����\��ł��B�@�m2014�N1��7���n
�w���ʂ������邱�Ƃ͗��v�������邱�Ƃ��i�O�j�x�@�ivol.5�j
�u������̂͂���Ō��\���e�����v�A�悭�����I���W�̂���ӂ��B���e���������x�ɕς���Ă���̂͂����h�B�u����ł��Ȃ������e���e�v�A�����҂��Ă��I�[��ɂ���Ԃ����b�l�ɏ悹���āA���܂݂�̍ŐV�s�_�C�G�b�g�}�V���������̈���苒���B�Ƃ��ǂ�����������Ŋ��Ă܂��B���e�b�͂��܂荡�ɂ��Č���Ȃ����̂��B
�������A���݂���͍̂������Ȃ��B�ߋ��͂��̐l�̋L���ɂ����Ȃ��i���̂��ߒʏ킻��͋r�F����A���҂��m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��j�A�����͒�`�ɂ�薢�����Ă��Ȃ��̂����瑶�݂��Ȃ��B�u����邩�H���ł���I�v�A�������Ȃ��̂����瓖��O�̂��ƂȂ̂ł������B�����āu�����ɍl������I�����̒����獡�����邱�Ƃ�I�Ԃ��H�v�A���̐l�̐��i�͂����ɂ��������B
��i�������Ɂu���v��������I�v�Ǝw������Ƃ��A���̂��Ƃ������Ă��邩�Ƃ����A����͕K�������̂��Ƃ��B���Z���i�P�N�ԁj�A�����i�U�����j�A�l�����i�R�����j�̂����ꂩ�̗��v�ڕW�ɑ��āA�u���v�ڕW��B������I�v�ƌ����Ă���̂Ɠ��ӂł���B�������v��������Ƃ����Ӗ��ł͎g���Ă��Ȃ��͂����B
���v��������Ƃ́A��������Ԃ̌�ɖڕW�Ƃ��闘�v���m�ۂ���Ƃ������Ƃ��B���������āu��Ƃ����ʂ�������v�Ƃ́A�u�����Ԃ�ʂ��ė��v���m�ۂ���v�Ɠ����Ӗ��Ƃ������Ƃ��B���̌����ƌ��ʂ̊W���������Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���ׂ����Ƃ́A���ʂ��o�����߂Ɍ��������邱�Ƃł���B���̌���������o�����Ƃ��A�}�l�W�����g���邱�Ƃ��B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŁA��Ƃ̐��ʂƗ��v�ɂ��Ă��������Ă��܂��B
�����v�͌����łȂ����ʂł���B�}�[�P�e�B���O�A�C�m�x�[�V�����A���Y���Ȃǂ̖ʂŊ�Ƃ����ʂ�������ƁA���̌��ʂƂ��ė��v��������̂��B�i�����j�����A���v�͐��ʂ��m���߂�̂ɖ𗧂B���ʂ��m���߂�ɂ͗��v�𑪂�ق��Ȃ��B��
�P�T���I���C�^���A�Ŕ������ꂽ������L���琶�܂ꂽ���v�Ƃ����T�O���A��Ƃ̐��ʂ𑪂邽�߂̕W���I�ȓ���Ƃ��āA�Q�P���I�܂ŕς�炸�g���������Ă���B�T�O�O�N�������Ă���ƊE�W���i�f�t�@�N�g�E�X�^���_�[�h�j�͋����B���ꂾ���D�ꂽ�����ł������ؖ����B��l�Ɋ��ӂ��āA���ʂ𗘉v�ő��点�Ă��炨���B
�Ƃ���ŁA�}�l�W�����g���邱�Ƃŗ��v�̌���������o���킯�����A�}�l�W�����g�����ʂƂ��ė��v�������邱�Ƃ��ł����Ƃ��A�}�l�W�����g�͉��ɐ��������Ƃ�����̂��낤���H
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŁA���v�̌����ɂ��Ă��������Ă��܂��B
�����v�́A�s�m�����Ƃ������X�N��������J���ł�����̂��B�o�ϊ����́A�����ł��邪�䂦�ɁA�����ɏƏ������ĂĂ���B�����A�����Ɋւ��Ă����ЂƂm���Ȃ̂́A�s�m�����Ƃ������X�N�����邱�Ƃ������B��
���ʂł��闘�v�̌���������o�����Ƃ���Ƃ��A�����̂��Ƃł���䂦�ɁA�ǂꂾ�����X�N����邩�����R�ɑI�����邱�Ƃ��ł���B�����Ԃ̗��v�̑傫���Ƃ́A��Ƃ����̊ԂɎ�������X�N�̑傫���ł������B��Ƃ��}�l�W�����g����Ƃ́A�����̗��v�Ƃ������ʂɑ��ă��X�N����邱�Ƃ��B
����͐��ʂƗ��v�ɂ��Ĉ��������l���Ă����\��ł��B�@�m2013�N12��16���n
�w�}�l�W�����g�Ƃ������t�ƃR�C���̗��\�i��j�x�@�ivol.4�j
�}�l�W�����g�̔ے�ʂ���̓I�ȉf���ŃC���[�W���Ă݂�B�f��X�^�[�E�E�H�[�Y�ŁA�������̃_�[�X�E�x�C�_�[���x�z����鍑���������B�����̓x�C�_�[�̖��߂ɑ��āu�x�d�r�C�l�x�@�k�n�q�c�i���̂Ƃ���A����l�l�j�v�Ɠ�����B�������߂ɋt�������A���s�����肷����̏�ő��݂��������B�����i�X�g�[���E�g���[�p�[�j�͓����\��̔����S�ʃw�����b�g�Ƒ��b���𒅗p�������A���߂ɒ����ɓ����悤�P������Ă���B���߂ɏ]�������Ȃ�A���͂Ȃ��ق����悢�B
�_�[�X�E�x�C�_�[�́A��ΓI�Ȍ��͎҂Ƃ��ċ��|�Ŏx�z���邽�߂ɁA�t�H�[�X�i�͂̌���j�̃_�[�N�E�T�C�h�i�Í��ʁj���g���B�t�H�[�X���g����\�͂����I�ꂵ�҂ł���B���Α��ɂ��郉�C�g�E�T�C�h�i�����ʁj���g���ɂ͍���ȌP�����K�v�����A�_�[�N�E�T�C�h�͋����{��A�����݂𗘗p����Ηe�ՂɎg�����Ƃ��ł���B���̂��߁A��Ƀ_�[�N�E�T�C�h�̗U�f�ɂ͕����₷���B
�t�H�[�X�̃��C�g�E�T�C�h�́A�W�F�_�C�̋R�m�����E�Ɏ��R�ƕ��a�������炷���߂Ɏg���B�鍑�̐ꐧ�Ɏx�z���ꂽ���E���玩�R��������邽�߂ɓ��������R�́A�t�H�[�X�̃��C�g�E�T�C�h���g���W�F�_�C�̋R�m���[�N�E�X�J�C�E�H�[�J�[�𒆐S�ɁA���u�ł��鑽�l�Ȍ��̃����o�[���ЂƂ̎����I�ȃ`�[���Ƃ��ċ@�\���Ă���B
�����ӎu��������ɗ�Âȃ��C�A�P�A���R�ō����I�����l�������n���E�\���A������ׂ�ŋC���ア���ʖ�łȂ�����L����b�R�|�o�n�A���Ȏ咣���Ȃ�������I�Ȏd��������q�Q�|�c�Q�A���t�ł͂Ȃ��s���ŃR�~���j�P�[�V��������`���[�o�b�J�B�鍑�̓����I�Ȑl�X�Ƃ͑ΏƓI�ɁA���I�ȃ����o�[�������̈ӌ������R�Ɏ咣���A���ꂼ��̋��݂����Ȃ��玟�X�ƌ����l�X�ȍ�����`�[���ŏ��z���Ă����B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŁA�}�l�W�����g�̍m��ʂɂ��Ă��������Ă��܂��B
���g�D�𒌂Ƃ��������I�ȎЉ�Ŏ��R�Ƒ�����ۂɂ́A�g�D�Ɏ��含�ƐӔC��^���A�������ʂ�����������̂��B��̕��@�ł���B�������A�g�D�ɐ��ʂ�����������̂́A�o�c�҂ƃ}�l�W�����g�̎d���ł���B�ꐧ������A��������g�����ɂ́A�}�l�W�����g���\���ȓ��������A�ӔC���ʂ��������Ȃ��B��
�t�H�[�X�̃��C�g�E�T�C�h�ƃ_�[�N�E�T�C�h�́A�}�l�W�����g�̍m��ʂƔے�ʂ̋�̓I�ȃC���[�W�ɋ߂��B�g�D�͕����Ă����ƒN�����_�[�N�T�C�h�̗U�f�ɕ����A�ꐧ�I�ȑg�D�ɂȂ��Ă��܂��X������݂��Ă���B�}�l�W�����g�̈Ӗ��i���l�j�Ƃ́A���̂��Ƃ�F�����Ȃ���A���C�g�E�T�C�h�i�}�l�W�����g�̍m��ʁj���猩���g�D�̂�����ւƓ������Ƃł͂Ȃ����B
�R�����iVol.1�j����l���Ă������Ƃ́A�u�Ȃ����}�l�W�����g�Ƃ������t������Ă���̂��v�A����������A�u�Ȃ��}�l�W�����g������̂��v�i�v�g�x�j�ɑ��铚�����B�������l����Ƃ��ɂ킽�������͂��i�v�g�`�s�j����l����Ȃ����Ă���B�Ⴆ�A�h���b�J�[�̌��t����āu�}�l�W�����g�Ƃ͌ڋq��n�����邱�Ƃ��v�Ɠ����āA�}�l�W�����g�ɂ��čl��������ɂȂ��Ă��܂��B
�������A�i�v�g�`�s�j�������ƁA������x���ꂢ����u�Ȃ����������Ă���̂��H�v�i�v�g�x�j�Ƃ����₢��������ł���B�u�}�l�W�����g�Ƃ́����ł���B�v�Əq�ꂩ����������߂ɁA���ł���u�}�l�W�����g�v���ꎩ�̂̈Ӗ����i�����̂��̂Ƃ��āj�����Ă��Ȃ����炾�B�Ӗ��𑨂��Ă��Ȃ�����u����Ă��Ӗ����Ȃ��v�Ƃ������_���o�₷���Ȃ�A�R�c�R�c�Ɛςݏd�˂Ă������g�݂����f����₷���Ȃ�B
���҂��o����������T�����Ă������ł́A�����ł��̂��Ƃ��l�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ōl���Ă��Ȃ�����A���͕�����������ɂȂ��Ă��邾���ŁA�{���͕������Ă��Ȃ��B�D�ɗ����Ă��Ȃ�����A���Ԃ��o�Ɩ����������₷���Ȃ�B
�i�v�g�x�j������������A���̌�́i�v�g�`T�j���i�g�n�v�j���i�c�n�j���i�b�g�d�b�j�j�̃T�C�N�����Ă����悢�B�T�C�N�����O�ɁA�i�v�g�x�j�𑨂��ċ��L���Ă������Ƃ�����B
����́u�}�l�W�����g�Ƃ͉����ǂ����邱�ƂȂ̂��v�A��̓I�Ɂi�v�g�`�s�j�Ɓi�g�n�v�j���l���Ă����\��ł��B�@�m2013�N12��2���n
�w�}�l�W�����g�Ƃ������t�ƃR�C���̗��\�i�O�j�x�@�ivol.3�j
�l�����̌��t�ɈӖ��������o���̂́A���̂��Ƃ�������A���̂��Ƃɂ��Ęb�����肷�邱�Ƃɉ��l������Ɗ�����Ƃ����B�u�Ӗ��Ȃ������I�v�ƌ����Ƃ��́A���̌��t���̂��̂ɈӖ����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���̂��Ƃ�������b�����肷�邱�Ƃɉ��l���Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���B
�}�l�W�����g�Ƃ������t�ɈӖ��������o����Ȃ���A�}�l�W�����g���Ȃ��ꂽ��A�}�l�W�����g�ɂ��Ęb���ꂽ�肷�邱�Ƃ͂Ȃ��B�}�l�W�����g������A�}�l�W�����g�ɂ��Ęb�����肷�邱�Ƃɉ��l������Ɗ����Ă͂��߂āA�ϋɓI�Ɏ��g��b�����肵�����Ȃ�B
���l��������Ƃ������Ƃ́A������悢�Ɗ�����Ƃ������Ƃ�����A�����ɂ�邢�Ɗ�����C���[�W���Ȃ��Ƃ悢�Ɗ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���錾�t�₠�邱�Ƃɉ��l���������Ƃ������Ƃ́A���ꎩ�̂ɍm��I�ȖʂƔے�I�Ȗʂ��ɔ��������Ƃ������Ƃ��B
���Ƃ��A���̐l�͗�������肢�Ƃ����Ƃ��A����i��肭�Ȃ��j�Ƃ����T�O�����邩��A��肢�Ƃ����Ӗ����͂�����Ɨ������邱�Ƃ��ł���B��肢�l�������ɂ́A����Ȑl���K�v�Ȃ̂��B�F����肩������A��肢�l�͏o�Ă��Ȃ��B
�}�l�W�����g�̈Ӗ����l����Ƃ��ɂ��A�}�l�W�����g����Ă��Ȃ���Ԃ��l���邱�ƂŁA�}�l�W�����g����Ƃ͂ǂ��������Ƃ��������Ă��邩������Ȃ��B�Ȃ����킩��Ȃ����A�}�l�W�����g���邱�Ƃ����A�}�l�W�����g���Ȃ����Ƃ̂ق����C���[�W���₷���B
�}�l�W�����g���Ȃ��Ƃ́A�l���W�܂����Ƃ��ɈӐ}�I�ȓ����������������Ȃ��Ƃ����C���[�W���B�ЂƂ�ЂƂ肪�����̎v�����܂܂ɏ���ɓ����o���B�Ƃ�����艽�����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ�����A�����Ȃ�ɍl���ē��������Ȃ��B�������A���ԂƂƂ��ɃJ�I�X��ԂɂȂ�A���������ŏՓ˂��N����B���������E���邽�߂Ƀ{�X���K�v�Ƃ���A�u����Ȃ��Ƃ�����ȁI�v�ƃ{�X�̎w���ɂ��g�D�ɗ͂ɂ�钁��������o���B
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŁA�}�l�W�����g�̔ے�ʂɂ��Ă��������Ă��܂��B
���g�D�����含�Ƌ���ȗ͂������A���ʂ��������������ꂽ��A����ɑ���̂͐ꐧ�ł����Ȃ��B�����̑g�D�����������������A��ΓI�Ȍ��͂��������ЂƂ�̐l���ɂ��x�z���͂��܂�B�ӔC�ɑ����ċ��|�����𗘂�����B��
����̓}�l�W�����g�̔ے�ʁi�R�C���̗����j���n�_�ɂ��āA���̔��Α��ɂ���m��ʁi�R�C���̕\���j���C���[�W���āA�}�l�W�����g�̈Ӗ��i���l�j�𑨂��Ă����\��ł��B�@�m2013�N11��15���n
�w�}�l�W�����g�Ƃ������t�ƃR�~���j�P�[�V�����i��j�x�@�ivol.2�j
�u�}�l�W�����g���āA�ڕW�Ǝ��т̍����Ǘ����Ă������Ƃ���ˁB�v�ƌ����A�u�}�l�W�����g���āA�l���ǂ��������Ă������Ƃ������Ƃł���B�v�ƕԂ��Ă݂�B�Ƃ��낪�u�ڕW�Ǝ��т̍����ǂ����߂邩�A�����ŊǗ�����̂��}�l�[�W���[�̎d������B�v���Ă������̘b�����ĂȂ��́H�u�Ⴄ��A�d��������̂͐l�Ȃ���Ј��̍s�����ǂ������o�������}�l�[�W���[�̎d������B�v�Ƌ��������Ă݂�B
�}�l�W�����g�Ƃ������t�ɂ��āA����ƈႤ�Ӗ��ő����Ă���悤���B�����ňӖ������荇�킹��X�e�b�v�ɐi�݂����̂����A�����������ӎ��̂����Ɂh�ǂ��炪���������h�̏����ɓ����Ă��܂��B������f�B�x�[�g�i���_�j�J�n�̃S���O���苿���B���_���i�ނɂ�Ă��݂��ɔM���Ȃ�A�������������Ԑ�ɂȂ�܂Ŏ����͑����B����Ȃ��ƂȂ猾�t�̈Ӗ��̂��Ƃ͐G��Ȃ���悩�����H
���錾�t�̈Ӗ��ɂ͈��͈̔͂�����A���̌��t�̈Ӗ����i��������t�Łj�������悤�Ƃ��Ă��A�ǂ��������I�ɂ��������ł��Ȃ��B���t�̈Ӗ������荇�킹��Ƃ́A����l�������I�ɐ������Ă��邱�Ƃ�ςݏd�˂Ă����āA�ł��邾�����̌��t�̑S�̂̈Ӗ��ɋ߂Â����ƂƂ�����B���̍�Ƃ����܂��i�߂A�ЂƂ�����`�[���ōl�����ق������̌��t�̖{���ɋ߂Â����Ƃ��ł���B�f�B�x�[�g�i���_�j�ł͂Ȃ��A�_�C�A���O�i�Θb�j�ŐV���ȈӖ���n�����Ă����B
�@�@�@�@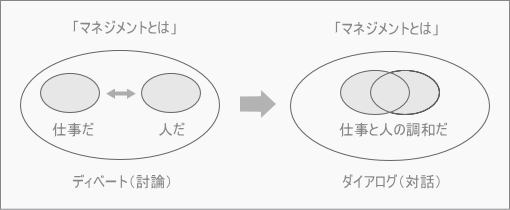
�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ŁA�u�d���v�Ɓu�d��������v�Ƃ͈Ⴄ�̂��ƌ����Ă��܂��B
���d���̓��m�̗̈�ɑ����A�l�ԂƂ͖��W�ȓƎ��̘_���������Ă���B�����A�d�������邱�Ƃ̓q�g�A�܂萶�����̗̈�ɑ�����B�����Ƃ��A�}�l�[�W���[�͏�Ɏd���Ɠ�����̗������}�l�W�����g���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�d���̐��Y�������߁A������̒B���ӗ~�����̂��B�d���Ɠ���������܂����a������K�v������B��
���������Ƃ��ɂ́A�ЂƂ̎��_�������Ȃ��Ƃ��܂����܂���B�������A���̖{������邽�߂ɂ͕����̎��_����������āA�ł�����葽���̐l�������ł��镁�ՓI�ȈӖ����Ƃ炵�o����Ƃ���ɂȂ��Ă���̂ł��B
���̃R�����ł́A�h���b�J�[�́w�}�l�W�����g�x����{�̋��ȏ��Ƃ��āA�K�x�ɑ��̖{�ŕ⑫���Ȃ���A�g�D�}�l�W�����g�̖{���𑨂��Ă����\��ł��B�@�m2013�N11��5���n
�w�}�l�W�����g�Ƃ������t�ƃR�~���j�P�[�V�����i�O�j�x�@�ivol.1�j
�N���Ƙb�����Ă���Ɓu����A�ǂ����b�����ݍ����Ă��Ȃ��ȁv�Ɗ�����u�Ԃ�����Ă���Ƃ�������܂��B����ȂƂ��́A�b���Ă��錾�t�i���ɃL�[���[�h�j�̒�`���Y���Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B
�}�l�W�����g�Ƃ������t�͎��R�ɐg�̂ɓ����Ă��邵�A�N���Ƙb�����Ă��Ă��u���ꉽ�H�v�ƕ�����邱�Ƃ͂܂�����܂���B�Ƃ��낪�A�����̂Ƃ�����f���Ă���Ƃ���Ɂu���ꉽ�H�v�ƕ������ƁA�ӊO�Ɠ��h���Ă��܂��܂��B�o�c�Ƃ��Ǘ��Ƃ������ɍڂ��Ă���������ꉞ���Ă݂܂����A�������������肵�܂���B���݂��Ɍo�c��Ǘ��Ƃ����Ӗ��ł��̌��t�͎g���Ă��Ȃ�����ł��B
����ꂽ���ԂŐ��Y�I�Șb������ɂ́A�{��ɓ���O�Ɂu�}�l�W�����g���Ă��������Ӗ�����ˁv�ƌ��t�̈Ӗ������荇�킹���Ԃ��������邩�ǂ����B���������������Ӗ����Ǝv���Ă��錾�t�́A����������v���Ă��邾�낤�Ə���Ɏv������Řb�����Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ̂ŁA���������o�ł��邩�ǂ������R�~���j�P�[�V�����̕�����ڂł��B
�}�l�W�����g�Ƃ������t�ɂ��āA�h���b�J�[�͒����w�}�l�W�����g�x�ł��������Ă��܂��B
���u�}�l�W�����g�v�́A���Ƃ̂ق�������t�ł���B���������A�����J�ɓƓ��̌��t�ł��邽�߁A���̌���ɂ͂��悻�悤���Ȃ��B�C�M���X�p��ɂ���Ȃ��B�u�}�l�W�����g�v�͐E�\��\���Ɠ����ɁA���̐E�\��S���l�X���w���B�Љ�I�Ȓn�ʁA����ɂ͂ЂƂ̐�啪��A������������Ӗ�����B��
���{��Ō��t�ɂȂ�Ȃ��T�O�A���ꂪ�}�l�W�����g�ł��B�������A�悭�l���Ă݂�Ό��t�ɂȂ�Ȃ����炱���A�l���ꂼ��Ɍł܂�������ς��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����炱���A�{�������ɍl���₷�����t�Ƃ������Ƃł��B
�g�D�}�l�W�����g�̖{���Ƃ͉����A�{�̒��̎t�������̗͂���Ȃ���A���̃R�����ōl�������Ă����܂��B�@�m2013�N10��1���n
�g�D�}�l�W�����g�̖{�����l����i�R�����̎�|�j
�\�Ɍ����ЂƂЂƂ̖��ɑΏ����Ă��A���̌��ɂ���{���I�Ȗ�肪��������Ȃ��Ԃ́A�������炩������ς��Ď��X�Ɩ�肪����Ă���B�����炽�����̍\�}�ł��B�n�ʂɊ���o�����������C�����ނ��Ă��A�n���ɂ��������̑���������Ȃ��Ǝ��X�Ɋ���o���B���������͂������ăQ�[������߂邪�A������̒��Ԃ͑��̒��ł݂�Ȍ��C�ɂ���Ă���B
���̊��Ԃɑg�D�̕ϊv�𐬌������邽�߂ɂ́A�g�D�}�l�W�����g�̖{���𑨂��āA���̕��@���l���A���s���Ă������Ƃ��K�v�ł��B���̃R�����́A�g�D�}�l�W�����g�̋��ȏ��i�ɂ��Ă���{�j���炻�̒m�b���w�сA�l�������邽�߂̏�ɂ��Ă����܂��B